歯の治療で神経を取ると聞くと、不安になる患者さんは少なくありません。特に、根管治療を受けた後に残根という状態になってしまうのでは、と心配される方もいらっしゃいます。残根とは歯の根だけが残った状態のことで、治療した歯がそうなってしまったらと不安になりますよね。本記事では、根管治療の基礎知識から、治療後に残根になってしまう原因や予防法、もし残根と診断された場合の対処法を解説します。
根管治療の基礎知識

残根について解説する前に、まずは根管治療の目的と実際の内容、そして根管治療を選択するのはどのような状況なのかについて解説します。
歯の神経を取る治療の目的
むし歯が深く進行して歯の神経(歯髄)に達すると、激しい痛みや腫れが生じます。この歯髄の炎症や感染は自然には治らず、放置すると歯の内部や顎の骨を溶かしてしまう恐れがあります。そこで根管治療といって、むし歯菌に感染した歯の神経や血管などの歯髄を取り除き、歯の内部を消毒する処置を行います。根管治療の一番の目的は、痛みや腫れなどの症状を取り除くことと、歯そのものを残すことです。歯の神経を取るのは歯を抜くこととは違い、あくまで歯を温存して機能を回復させるための治療なのです。
根管治療を選択するケース
では、どのような場合に根管治療が必要になるのでしょうか。一般的には、むし歯が歯の内部の神経まで達してしまった場合に根管治療を行います。歯髄までむし歯菌に侵された状態になると、神経を除去する処置が必要になりますまた、むし歯以外でも歯が外傷で折れて神経が露出・感染した場合や、過去に受けた根管治療の再感染などでも、根管治療が選択されることがあります。いずれにせよ、歯の神経が生きたままでは治せないほどのダメージを受けているケースで、歯をできるだけ抜かずに済ませるために根管治療が行われます。
根管治療の内容
根管治療では、歯の中の細菌に感染した神経組織を取り除き、内部を清潔にしたうえで密閉する治療です。まず局所麻酔をして痛みを感じないようにしてから、歯の上部に小さな穴を開けてむし歯に侵された歯質や歯髄を露出させます。次に、細い針金状の器具を使って、歯の根管内にある感染した神経や組織をかき出します。薬剤で根管内を洗浄・消毒し、細菌ができるだけ残らないようにします。根管のなかに専用の充填材を隙間なく詰めて密封し、細菌の再感染を防ぎます。最後に、削った歯に仮詰めをした後、数回の治療で根管がきちんと消毒・充填できた段階で、被せ物や詰め物を作って歯の形を補強します。
根管治療における残根とは

根管治療を行っても、なかには残根という状態になることがあります。では、残根の状態は起こるのでしょうか。また、残根はどのような影響を及ぼすのかを本章では解説します。
残根とは
残根とは、歯として機能するために必要な歯の頭の部分(歯冠)がむし歯などによって溶けて失われ、歯の根だけがお口のなかに残っている状態の歯のことです。残根になった歯は見た目に歯がないだけでなく、通常の噛む機能もなくなります。残根は加齢や過去の治療により歯が脆くなっていたり、長年にわたってむし歯を放置していたりすると、結果的に残根状態の歯が増えてしまうのです。残根は後述するように、放置するとお口の中や全身に悪影響を及ぼす可能性もあるため、対処が必要な状態です。
残根になる原因
根管治療を受けた歯が残根になってしまうのは、いくつかの原因が考えられます。主な原因を順番に見ていきましょう。
再感染や不完全な治療
根管治療後に残根になってしまう大きな原因の一つは、治療の不完全さや細菌の再感染です。神経を抜いた後に最後まで処置をせず放置すると、歯の内部に細菌が入り込み再びむし歯が進行してしまいます。また、治療自体は最後まで行っても、根管内の消毒が不十分だったり、詰め物が隙間なく入っていなかったりすると、時間経過とともに細菌が再感染して内部でむし歯や炎症が再発し、残根になってしまうことがあります。根管治療がもし何らかの理由で十分な処置が行えなかったり、その後の被せ物がきちんと密着していなかったりすると、せっかく治療した歯が再度むし歯に侵され、残根になってしまうリスクが高くなります。
治療後の歯の破折
根管治療を行った歯は、神経や血管がなくなった分どうしても脆くなり、割れたり折れたり(歯根破折)しやすくなります。治療後の歯の破折によって歯冠部が失われ、結果として残根状態になる場合もあります。歯が割れる原因としては、治療後の歯そのものの強度低下に加え、歯ぎしり・食いしばりなど過度な力が習慣的に加わることも大きな要因です。
むし歯の再発や放置
根管治療が終わった後でも、新たにむし歯が再発したり、治療後のケアを怠ったりすると残根につながることがあります。また、被せ物自体が取れなくても、その縁から二次的にむし歯が発生することがあります。特に口腔衛生の習慣が不十分な場合や、甘いものを頻繁に摂取する生活を続けていると、治療した歯でも再びむし歯になるリスクが高まります。一度治療した歯だからといって油断せず、毎日の丁寧な歯みがきやフッ素ケアでむし歯の再発を防ぐことが大切です。
残根になりやすい状態
まず、重症なむし歯で歯の大部分が溶けてしまっているケースでは、治療後も歯の構造自体が脆く、再発や破折によって残根になるリスクが高くなります。特に、神経を取った歯で歯の壁が薄くなっている状態では、早めに全周を覆うかぶせ物で補強しないと、噛む力で割れやすくなります。また、根管治療を途中で中断してしまった場合や被せ物が取れたまま放置している場合も、残根になる可能性があります。さらに、歯ぎしり・食いしばりの癖がある方や、むし歯のリスクが高い生活習慣(不十分な歯磨きや頻繁な間食)をお持ちの方も、治療した歯が再びダメージを受けて残根化しやすい状態といえるでしょう。
残根の状態が引き起こすリスク
一見、根だけが残った歯は「痛くもないし放っておいても平気なのでは?」と思われがちですが、それは誤りです。残根をそのまま放置すると、さまざまなリスクやデメリットが生じます。
歯茎の腫れ
残根状態の歯は、内部に感染が残っていたり清掃が行き届かなかったりするため、歯茎の腫れや膿が出る原因になります。特に、歯の根が歯茎のなかに隠れてしまっている場合、ある日突然歯茎が腫れ上がって痛み出すこともあります。痛みがないからといって残根を放置せず、早めに歯科で適切な処置を受けることが大切です。高齢の方では、残根を放置することでお口の中の細菌が増殖し、免疫低下時に誤嚥性肺炎など全身の感染症リスクを高める恐れがあります。痛みがないからといって残根を放置せず、早めに歯科で適切な処置を受けることが大切です。
歯並びや噛み合わせへの影響
残根状態の歯はそのまま何も対処しないでいると、ほかの歯の歯並びや噛み合わせに悪影響が出てきます。放置期間が長いほど歯列の乱れは顕著になり、将来的に噛み合わせの不調を引き起こすこともあります。また、噛む力のバランスが崩れることで特定の歯に過度な負担がかかり、ほかの歯も痛めてしまう可能性があります。このように残根放置はお口全体の健康に関わる問題ですので、早期に適切な対策が必要なのです。
残根と診断されたときの治療法

残根が引き起こすリスクがあるのはわかっていただけたと思います。本章では残根に対する治療法に関して、再根管治療と抜歯に分けて解説します。
再根管治療
残根状態になった歯でも、歯根がしっかり残っており、感染を抑えれば再び土台として使える場合には、再度根管治療を行って歯を保存できる可能性があります。これを再根管治療と呼び、過去に根管治療を行った歯に対してもう一度行う神経の治療です。残根状態の歯は神経がすでに死んでいるか過去に取ってあることが多いので、歯の神経を残すことはできません。その代わりに、根管治療で作った穴(根管)に金属やレジン、ファイバーなどで土台をつくり、その上に人工の歯冠をかぶせて歯の形を復元します。こうすることで、再び噛める歯の形に戻すことが可能です。
抜歯
残念ながら、どのような場合でも歯を残せるわけではありません。歯根に亀裂が入っている場合や、歯の根っこの長さが短すぎて土台が立てられない場合、あるいはむし歯が歯茎の深い部分まで進行して歯根までボロボロになっている場合などは、残根の周囲に常に炎症が起きていたり物理的に再建が困難だったりします。このようなケースでは、抜歯によって残った根を取り除くのが適切な治療法となります。抜歯自体は局所麻酔下で行いますので痛みはほとんど感じません。抜歯後、傷口が治るのを待ってから、インプラントなど失った歯を補う治療を検討します。
残根を防ぐためにできること

根管治療後に歯を残根状態にしないためには、治療後の予防策がとても大切です。以下に、日常生活で心がけたいポイントを紹介します。
歯ぎしり・くいしばりをコントロールする
何度も述べたように、歯ぎしりや食いしばりの癖があると歯に大きな力がかかり、特に根管治療後の歯は割れやすくなります。しかし、こうした力のコントロールは、自分の意識だけでは限界があります。そこで有効なのが、ナイトガード(就寝時マウスピース)の使用です。歯科医院で自分の歯型に合わせたマウスピースを作り、夜寝るときにはめて寝ることで、歯ぎしりの衝撃から歯を守ることができます。ナイトガードは歯のすり減り防止や顎関節の負担軽減にも役立ちます。また、日中も無意識に食いしばっていないかときどき自分でチェックし、力が入っていたら力を抜く癖をつけましょう。ストレスや疲労も食いしばりの原因になるので、リラックスできる環境を整えることも大切です。こうした工夫で歯にかかる余分な力を減らし、治療した歯を保護しましょう。
むし歯を進行させない生活習慣を心がける
残根を防ぐには、新たなむし歯を作らない・進行させないことが不可欠です。日々の口腔ケアと生活習慣を見直し、むし歯リスクを下げましょう。まず基本は、丁寧な歯磨きです。毎食後なるべく早めに歯を磨いて、歯垢とその中の細菌をしっかり除去することが重要です。特に寝る前の歯磨きは時間をかけて念入りに行いましょう。また、フッ素配合の歯磨き粉を使う習慣も効果的です。フッ素には歯の表面のエナメル質を強化してむし歯菌の出す酸に溶けにくくする作用や、初期のむし歯部分を再石灰化して修復する働きがあります。さらに、甘いものや間食の頻度を見直すことも大切です。砂糖を含む飲食物をだらだら摂取しているとお口の中が常に酸性に傾き、むし歯が進行しやすくなります。おやつは時間と量を決め、食べた後はうがいや歯磨きをしてお口を中和しましょう。こうした習慣を心がけることで、治療した歯を再びむし歯にさせず健全な状態を保つことができます。
定期的に歯科検診を受ける
歯科での定期検診・メンテナンス、これもとても重要です。根管治療をした歯はもちろん、ほかの歯も含めて、定期的に検診を受けることでトラブルの早期発見・早期対応が可能になります。一般的には少なくとも半年に1回、できれば3~4ヶ月に1回のペースで歯科検診を受けるのが望ましいでしょう。また、専門的なクリーニング(PMTC)で普段の歯磨きでは落としきれない汚れを除去すれば、むし歯や歯周病の予防効果も期待できます。
まとめ
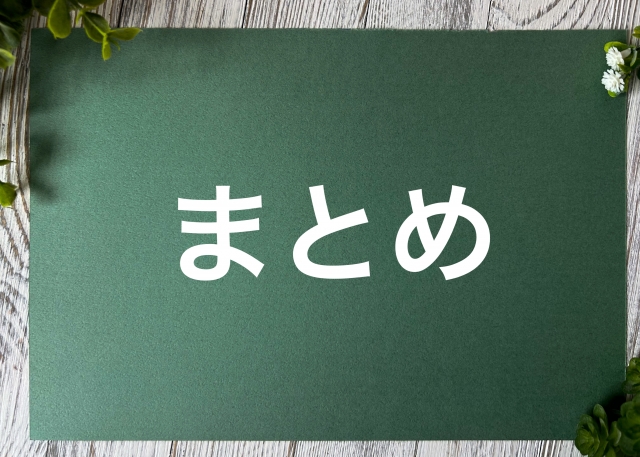
根管治療後に歯が残根になってしまうのではないかという不安は、誰しも抱くものです。しかし適切な治療とその後のケアを行えば、多くの場合、歯は長く機能させることができます。今回ご説明したように、根管治療は歯を残すための大切な処置であり、残根を避けるためには治療を最後までしっかり受け切ること、治療後に歯を適切に補強すること、そして日々のセルフケアと定期検診で再発と破折を防ぐことが重要です。万一残根になってしまっても、歯科医は可能な限り歯を救う方法を考えてくれますし、抜歯が避けられない場合でもその後の選択肢があります。大切なのは、放置せずにすぐ相談することです。歯は一度失うともとには戻りません。根管治療を受けた歯も含め、ご自分の歯を少しでも長く健康に保つために、今回の記事がお役に立てば幸いです。
参考文献
