根管治療は、むし歯が歯の神経(歯髄)にまで達してしまった場合に行う治療法です。神経を取り除くため、治療前後にズキズキとした痛みを感じることは多く、不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では根管治療前後のズキズキとした痛みについて以下の点を中心にご紹介します。
- 根管治療とは
- 根管治療前の痛み
- 根管治療後の痛み
根管治療前後のズキズキとした痛みについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
根管治療とは

根管治療は、深刻なむし歯が原因で歯髄(歯の神経)に感染が生じた場合に行われる処置です。根管治療は、歯の内部の感染を除去し、将来的な感染の再発を防ぎながら歯を保存することを目的としています。
根管治療の手順
- 診断と計画:歯科医はまず、詳細なレントゲン撮影と視覚検査を通じて、感染の程度と根管の形状を評価します。これにより、治療計画が立てられます。
- 局所麻酔とアクセス開口:治療が始まると、患部の感覚を麻痺させるために局所麻酔が行われます。その後、歯科医は歯の上部を開け、根管へのアクセスを確保します。
- 感染物質の除去:特殊な器具を用いて、感染した神経組織や細菌、死んだ細胞を取り除きます。これにより、根管内部がクリアになります。
- 清掃と消毒:根管内部は、細かなファイルと洗浄液を使用して徹底的に清掃されます。清掃と消毒は、感染の残留物を完全に除去し、根管を消毒するために不可欠です。
- 根管の充填と封鎖:清掃後、根管内部はガッタパーチャという特殊な材料で充填されます。その後、一時的な充填材または恒久的な冠で歯を封鎖します。
- 仕上げと修復:根管治療が完了した歯は、強度が低下しているため、歯を補強するためにクラウン(人工の歯冠)でカバーされます。これにより、歯の機能が回復し、見た目も改善されます。
根管治療は、複数の診療が必要な場合が多く、完了までに数回の通院が必要です。治療後も定期的なフォローアップが推奨され、治療した歯の健康を維持するための検査が行われます。
根管治療前の痛み①慢性期

ここからは、根管治療前の痛みのなかでも、症状が穏やかな「慢性期」について解説します。慢性期の原因や症状、歯科医院での適切な処置について理解することで、不安を軽減し、適切な治療を受けられます。
慢性期の痛みと症状
根管治療を受ける前の慢性期における痛みは、日常生活に影響を及ぼすことがあります。この段階での症状は以下のとおりです。
- 感度の変化:温冷刺激に対する過敏性が増します。
- 持続する痛み:軽度だが一定の痛みが続きます。
- 夜間の痛み:横になると痛みが強くなることがあります。
これらの症状は歯の神経に感染している可能性を示しており、適切な治療を受けることが重要です。慢性期の痛みが見られる場合は、早めに歯科医を訪れ、根管治療の適用を相談してください。
歯の状態
根管治療前の慢性期は、軽度の痛みしか感じませんが、その内部では深刻なダメージが進行していることがあります。慢性期では、歯髄(血管や神経を含む歯の内部組織)が壊死しており、歯根の先端に膿が溜まっている状態になります。この状態は、突然激痛を引き起こし急性期へと移行するリスクがあります。
この症状が現れた場合、歯の中の問題がすでに進行している可能性があり、放置すると急性の激しい痛みに襲われることもあります。したがって、こうした痛みや不調を感じた際は、速やかに歯科医院での診断を受けることが推奨されます。
根管治療は必要?
慢性期の根管治療前の痛みには、根管治療が必要です。根管治療を行わないと歯を抜かなければならない状態になる可能性があるため、注意が必要です。
痛みが出たときには以下のような対応を取りましょう。
すぐに痛みを抑えるために
- 市販の痛み止めの服用:慢性的な歯の痛みに対して、市販の鎮痛剤(非ステロイド性抗炎症薬など)を使用することが推奨されます。これにより、一時的に痛みを軽減することが可能です。
- 歯科医院での応急処置:かかりつけの歯科医に相談し、痛みの原因を特定してもらいましょう。必要に応じて噛み合わせを調整し、歯を休ませる処置を行うことがあります。
痛みの原因を取り除くために
- 根管治療を実施:慢性の痛みが持続している場合、それは歯の内部に深刻な問題(むし歯や歯髄の感染)していることを示しています。根管治療によって感染した歯髄を取り除き、根管を清掃・消毒し、充填することで、痛みの原因を根本から解消し、歯を保存できます。
痛みが出た場合に市販薬で一時的な緩和は可能ですが、根本的な問題を解決するためには、専門的な治療が不可欠です。歯の状態がすでに深刻である場合、根管治療を受けることで、痛みの原因を取り除き、歯の健康を長期的に保てます。
根管治療前の痛み②急性期

根管治療前の痛みのなかでも、耐え難いほどの激痛が現れる「急性期」について解説します。 急性期の原因や症状、そして緊急性の判断基準を理解することが大切です。
急性期の痛みと症状
根管治療前の急性期の痛みは、日常生活に大きな影響を及ぼします。主な症状は、以下のとおりです。
- 鋭く激しい痛み:歯の神経が極度に刺激されることで、ズキズキとした鋭い痛みが生じます。痛みは持続的で夜間でも痛みが和らぐことは少なく、睡眠を妨げるほどです。
- 体温の上昇と全身のだるさ:感染の影響で微熱が出ることがあり、体全体にだるさを感じることがあります。
- 噛む際の痛み:噛み締める動作で痛みがさらに強くなるとされています。
- 腫れ:感染が進行すると、関連する歯肉が腫れ、重症の場合は顔の腫れが目の下や首まで広がることもあります。また、喉の腫れを伴うことで食事や飲水が困難になる場合もあります。
- 痛み止めの効果が期待できない:通常の痛み止めでは効果が期待できず、処方薬が必要になることもあります。
このような急性期の症状は、迅速な医療介入が求められます。激しい痛みやその他の症状が現れた場合は、速やかに歯科医院に行き、適切な治療を受けることが重要です。
歯の状態
歯の根の先端に位置する根尖部で、歯髄(血管や神経が含まれる部分)が壊死し、膿が溜まっている状態です。この状態を急性化膿性根尖性歯周炎と呼ばれ、内部の圧力が上昇し、強烈な痛みを引き起こします。この痛みは数時間から数日間続くことがあり、最終的には慢性痛に移行する可能性があります。
また、歯髄が完全に壊死していない場合でも、歯髄に炎症が生じている(歯髄炎)ことで、類似した症状が現れることがあります。
このような急性期の痛みは、日常生活に著しい影響を及ぼし、治療の遅れが更なる合併症を引き起こすため、迅速な医療対応が必要です。歯科医はこの状態を評価し、感染の拡大を防ぐために早急に根管治療を行うことが一般的です。
根管治療は必要?
先述のとおり、急性期の痛みは感染や炎症が進行し、強い痛みや腫れを伴うため、悪化を防ぐために根管治療は必要です。
根管治療は、痛みを大幅に減少させるとともに、歯の健康を長期的に維持することが可能です。急性期の症状が見られる場合、早期に治療を行うことで、より大きな合併症を避けられます。
根管治療後の痛み

歯の神経を取り除くため、治療後に痛みを感じるケースが多くあります。しかし、適切な対処法を知ることで、痛みを軽減し、スムーズな回復を促せます。 ここからは、痛みの原因と、それぞれの対処法について解説していきます。
痛みの症状
根管治療後には、さまざまな痛みが現れることがあります。主に以下の症状が現れます。
- ズキズキする痛み:治療部位の免疫反応が活性化し、組織の修復が行われる過程で生じます。特に治療直後に痛みが生じますが、膿を排出しようとする身体の反応によるものです。
- 鈍痛:根管内の組織が正常に回復する過程で、治療後数日間にわたり続く軽いが持続的な鈍痛が感じられることがあります。
- 圧痛:歯を噛むと痛みを感じることがあり、これは根管内部の圧力変動によって生じます。
- 炎症による痛み:治療部位の周囲、特に歯茎が腫れた場合に発生する痛みです。この腫れは、治療による直接的な刺激から生じます。
これらの痛みは、根管治療が原因で起こる正常な反応の一部ですが、痛みは時間とともに減少し、適切なケアと経過観察により解決されます。しかし、治療後に痛みが長引く場合は、追加の治療が必要になることもあるため、歯科医との定期的なフォローアップが重要です。
痛みの原因
根管治療後の痛みは、治療中に感染物質や炎症を取り除いた一時的な刺激だけでなく、以下のようなさまざまな要因によって引き起こされることがあります。
- 取り残された神経:根管内の組織が複雑であるため、ときには歯の神経の一部が完全に除去されずに残ってしまうことがあります。これが痛みの原因となることがあります。
- 根管内の膿:根管の先端やその内部に膿が溜まっている場合、これが原因で歯茎の腫れや痛みが発生します。
- 歯根膜の炎症:歯根膜が炎症を起こすと、食べ物を噛む際に痛みが生じることがあります。これは歯にかかる圧力を感じる部分であるため、とても敏感です。
- 薬剤の圧力:根管内に詰められた薬剤によって圧力がかかり、これが痛みの原因となることがあります。痛みは通常数日で解消しますが、長引く場合は再診が必要です。
- 歯根の破折:歯根が破折していると、細菌の侵入や膿の形成が起こりやすく、これによって歯肉の腫れや痛みが生じます。
根管治療後の痛みは、数日から1週間程度で自然に治まりますが、長引くこともあるため注意が必要です。
痛みの対処法
根管治療後の痛みは一時的なものですが、適切な対処法を用いることで管理することが可能です。対処法は以下のとおりです。
- 痛み止めの服用:根管治療後に感じる痛みは、しばしば激しいものですが、歯科医師が処方する痛み止めの適切な使用で軽減できます。医師の指示に従い、適切なタイミングで痛み止めを服用してください。
- 冷却療法の適用:患部が腫れている場合や痛みが強いときには、外側からタオルで包んだ氷の袋を患部に適用するといいでしょう。ただし、長時間の冷却は避け、20分ごとに休憩を取るようにしてください。
- 活動の制限:治療後は、激しい運動や熱い飲食物、アルコールの摂取を避けることが痛みの悪化を防ぐために推奨されます。これにより体温の上昇を避け、痛みの増加を抑えます。
もし痛みが数日間持続する場合や、通常の活動に支障をきたすほどであれば、追加の診察を受けることが必要です。この場合、再根管治療が必要になることもありますので、早めに歯科医師に相談することが大切です。
再根管治療が必要な場合

再根管治療は、以前に行われた根管治療が成功しなかったり、後に問題が発生したりした場合に必要になる処置です。この治療が必要になる具体的なケースは以下のとおりです。
- 症状が現れる:根管治療後に「膿が出る」「歯茎を押すと痛い」「噛むと痛い」などの症状が持続する場合、これらは根尖性歯周炎の兆候であり、再根管治療が必要です。
- レントゲンによる診断:歯科医院での定期的なレントゲン検診で根尖性歯周炎が確認された場合、患者さんに自覚症状がなくても、進行を防ぐための再根管治療が推奨されます。
- 被せ物や詰め物の交換:古い被せ物や詰め物を新しいものに交換する際、下の歯の根管治療の状態を再評価し、必要に応じて予防的な再根管治療を行うことがあります。
- むし歯の進行:根管治療を受けた歯は、神経がないためむし歯の進行に気付きにくいとされています。根管内までむし歯が進行していた場合、微小な漏洩が起こっている可能性があり、再根管治療が必要です。
これらのケースでは、早期の介入により症状の悪化を防ぎ、歯を長持ちさせられます。痛みがある場合や症状が見られる場合は、適切なタイミングで歯科医に相談し、必要な治療を受けることが重要です。
まとめ
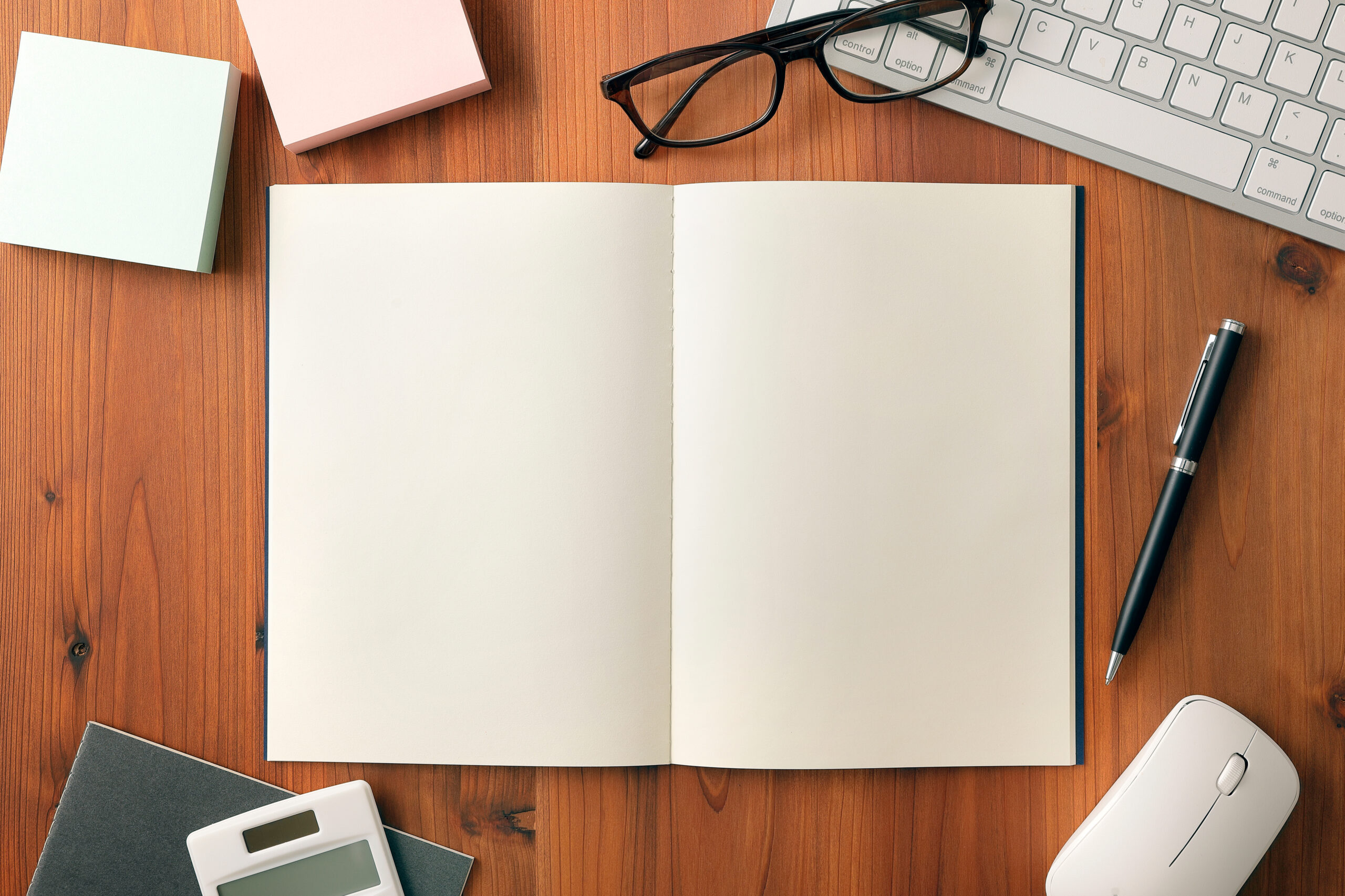
ここまで、根管治療前後のズキズキとした痛みの原因や対処法について解説しました。
要点をまとめると、以下のとおりです。
- 治療で根管内の感染源が除去された後、身体の免疫反応が活発になり、膿を排出しようとするため、痛みがでる場合がある
- お風呂や運動、アルコールなど、体温が上がるような行為を避けることで、痛みの管理が可能
- 根管治療は、むし歯治療よりも複雑で時間がかかるため、複数回の通院が必要になることがある
根管治療前後のズキズキとした痛みは、感染や炎症が原因で発生することが多く、適切な対処が必要です。根管治療を受ける際は、治療の必要性を理解し、適切なケアを行うことで、痛みを抑え、健康な歯を保てるように気を付けましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
