根管治療は、深いむし歯などで歯の内部にある神経(歯髄)が炎症や感染を起こした際に行う治療です。自分の歯を残すために重要な治療ですが、複数回の通院が必要になるケースが多く、治療期間が長くなりがちです。本記事では、根管治療の標準的な通院間隔や回数、通院の間隔が空きすぎてしまった場合のリスクと対処法、さらに短期間で終わる根管治療の可否やそのメリット・デメリットを解説します。
標準的な根管治療の通院間隔と回数

- 根管治療の通院間隔を教えてください
- 根管治療では通常、約1週間に1度のペースで通院します。毎日連続して処置をしても効果が高まるわけではなく、根管内に入れた薬剤を作用させるためにある程度の間隔を空けることが望ましいからです。治療直後は痛みや違和感が続くこともあるため、短すぎる間隔で通院してもメリットはなく、週1回程度のペースが適切とされています。なお患者さんの症状や治療段階によっては、初期は1週間毎、炎症が落ち着けば2週毎といったように調整することもあります。いずれの場合も、薬の効果が持続している間に次の処置へ進み、唾液や細菌の侵入を防ぐことが重要です。
- 根管治療の通院回数は何回程度ですか?
- 根管治療は1回の通院で完了することは基本的にありません。症例によりますが、一般的には2~4回程度の治療で根管内の清掃・消毒と充填までを行います。
例えば、前歯の根管は1~2本と少ないため2~3回の処置が目安ですが、奥歯は根管が3~4本あるため消毒処置だけで3~4回かかり、全体として平均5~7回ほどの通院が必要になるとされています。また、根管治療自体が終わった後も、削った歯を補強する土台や被せ物(クラウン)を装着するためにさらに数回通院する必要があります。したがってトータルでは1~2ヶ月程度(5~7回前後)の通院を見込んでおくのが一般的です。ただし歯の状態や難易度によって治療回数は増減し、感染が広がっている場合や根管の形が複雑な場合は清掃・消毒に時間がかかるため回数が増える傾向にあります。
逆に歯の神経が死んでおらず感染が軽微なケースでは2~3回で完了することもあります。いずれにせよ、保険診療の場合は1回の診療時間に制限があり、一度に処置できる範囲が限られるため結果的に通院回数が増える可能性がある点も留意しましょう。
- 複数の歯で根管治療が必要な場合の通院頻度も教えてください
- むし歯や歯の痛みが重なり複数の歯に根管治療が必要となるケースでは、基本的に一本ずつ順番に治療を行います。その場合も通院頻度については変わりません。1回の診療で処置できる範囲や内容が制限されており、同じ日に二本の歯の根管治療を同時進行することはできない場合があります。そのため、歯科医は症状の優先度を判断したうえで緊急度の高い歯から順に治療していきます。自由診療であれば長時間の枠を確保して二本以上をまとめて治療することも技術的には可能ですが、その場合でも治療時間が大変長くなる負担や費用増の問題があります。複数の根管治療が必要な場合こそ、歯科医師と相談のうえ計画的に通院し、それぞれの歯を最後まで治療しきることが大切です。
根管治療の間隔が空きすぎてしまったときの対処法

- 根管治療中に通院をやめるリスクを教えてください
- 根管治療は途中で中断するととても危険です。治療では毎回、根管内を消毒した後に細菌が入らないよう仮の詰め物(仮封)をしますが、この仮封の効果は永続しません。患者さんが自己判断で通院を止めてしまうと、時間の経過とともに仮封が取れたり隙間ができて、消毒中の根管内に再び細菌が侵入してしまいます。その結果、痛みや腫れがぶり返すだけでなく、せっかく取り除いたはずの箇所に再度むし歯菌が繁殖し、感染が根の先まで広がる恐れがあります。最初は歯を残せる状態でも、数ヶ月も放置すればむし歯が大きく進行して歯を保存できなくなるケースすらあります。歯科医師の指示どおり最後まで通院し、途中で中断しないようにしましょう。
- 根管治療の間隔が1ヶ月以上空いてしまったら歯はどうなりますか?
- 目安として3週間以上通院の間隔が空くと、仮封の効果が低下し始めて細菌が再侵入するリスクが高まるとされています。したがって1ヶ月も放置すれば多くの場合、根管内で細菌が再び繁殖して炎症や痛みを引き起こす可能性が高いでしょう。患者さんの自覚症状がなくても、見えない部分で感染が進行している恐れがあります。また、長期間放置することで治療の効果が上がりにくくなり、最終的な成功率にも悪影響が及ぶ可能性があります。
- 根管治療の間隔が空きすぎたのですが治療をしてもらえますか?
- はい、間隔が空いてしまっても諦めずに早急に歯科医院を受診してください。歯科医師はまずレントゲンなどで現在の歯の状態を詳しく評価し、歯を残せるかどうかを判断します。再治療で対応できる場合は、あらためて根管内を清掃・消毒し直してから治療を再開します。一方、残念ながら内部のむし歯が大きく進行して歯根まで崩壊している場合などは、抜歯を検討せざるをえないケースもあります。間隔が空いた期間が長いほど歯の予後は厳しくなるため、「今さら通院しても無駄かも」と自己判断せずできるだけ早く治療を再開することが肝心です。
- 根管治療の間隔が空いているときに気を付けることを教えてください
- 何らかの事情で次回の通院まで長めの間隔が空いてしまうことが事前にわかっている場合は、早めに歯科医師に申し出ておくことが大切です。事前に伝えておけば、通常より長持ちする仮封材に変えるなどの対応が可能だからです。出張で1ヶ月来られないなど予定が判明した時点で、必ず担当医に相談しましょう。
また、治療中~治療後の歯は神経を取って脆くなっており、特に仮の詰め物をしている間は過度な力や衝撃を与えないよう注意してください。硬い物を噛んだ拍子に仮封が外れたり、歯自体が割れてしまうリスクがあります。不安定な仮詰めの状態で長期間過ごすのは望ましくないため、なるべく治療中の歯では硬い食べ物を避けて噛まないようにしましょう。
加えて、口腔内の清潔にも一層気を配ってください。仮封の隙間から細菌が入るのを防ぐため、食後の歯磨きやうがいを徹底し、甘い物が歯に残らないようにすることが大切です。治療の間隔が空いている間も、痛み・腫れなど異常を感じたら我慢せず早めに受診しましょう。
短期間で終わる根管治療とは

- 短期間で終わる根管治療はありますか?
- 症例によっては、根管治療を1~2回の通院で完了させることも可能です。特に根管内の感染がほとんどないケースでは、歯髄の除去から根管充填までを一回の診療で連続して行う単回法(一回法)が選択されることがあります。近年の歯内療法のガイドラインでも、無菌的な処置と適切な根管充填が確実に行える条件下であれば、複数回よりも1回で完了する方法を採用してもよいと報告されています。
ただし、保険診療では1回あたりの治療時間に限りがあり長時間の処置が難しいため、短期間で完結させるには自費診療で十分な時間を確保する必要がある点に注意が必要です。また、症状が重度なケースや膿が出ているような感染根管では、無理に一回で終わらせず複数回に分けて消毒を繰り返す方が安全な場合もあります。短期間で終わるかどうかは歯の状態によりますので、担当医と相談のうえ適切な治療計画を立ててもらいましょう。
- 短期間で終わる根管治療のメリットとデメリットを教えてください
- 短期間で根管治療を完了させることには以下のようなメリットとデメリットがあります。
【メリット】
通院回数が少なく患者さんの負担が軽減されることが大きなメリットです。1本の歯の根管治療に1~2ヶ月かける従来法に比べ、短期間で治療が終われば仕事や生活への支障が少なくなります。また、治療途中で通院を中断してしまうリスクを減らせる点も利点です。さらに、早期に根管が封鎖されるため治療中の再感染リスクが下がる可能性もあります。
【デメリット】
一度の診療時間が長くなりやすいため、患者さんにとって肉体的・精神的負担が大きい場合があります。また、短期間で処置を完了するためには高度な技術と設備が必要であり、保険の範囲では難しいため費用が高額になる傾向があります。また、術後の痛みが強まるリスクが指摘されています。さらに、感染が残った状態で無理に根管を封鎖すると治療の失敗(再感染)の可能性が高まるため、症例の選択を誤るとデメリットが大きくなりえます。
編集部まとめ
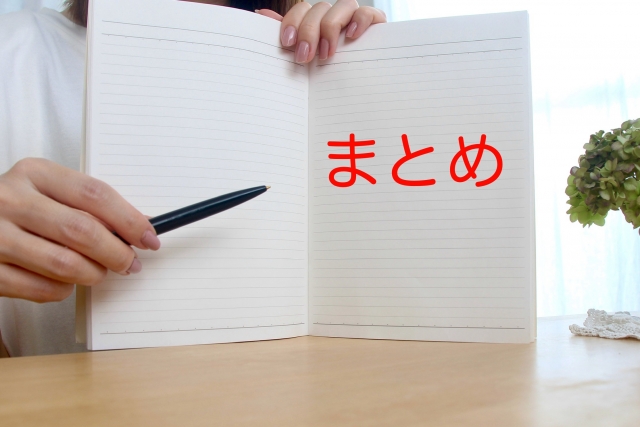
根管治療の成功には患者さん自身が計画どおり通院を完遂することが欠かせません。標準的には週1回ペースで数回~十数回の通院が必要であり、途中で間隔が空きすぎると再感染のおそれが高まります。やむをえず治療の中断や遅延が生じそうな場合は、必ず事前に歯科医師へ伝え、適切な対応策を講じてもらいましょう。万一、期間が空いてしまった場合でもできるだけ早めに受診を再開すれば、歯を救える可能性があります。最近では症例によって短期間で終わる根管治療も行われていますが、最優先すべきは確実に感染を除去し歯を保存することです。通院回数や期間について不安がある方は、遠慮なく担当医に相談し、ご自身にとって最善の治療計画を立ててもらってください。大切な歯を長持ちさせるためにも、根管治療は最後まで受け切ることが肝心です。
参考文献
