根管治療中にやってはいけないことはあるのでしょうか?
根管治療は通常のむし歯の治療と異なるため、むし歯治療中と同じようにいかない場合もあります。
本記事では、根管治療中にやってはいけないことについてご紹介します。
- 根管治療中に気を付けたいこととは
- 根管治療でトラブルが起きた場合にやってはいけないこととは
- 根管治療で避けたい歯科医院とは
根管治療を始めた方は、ぜひご参考いただけますと幸いです。
そもそも根管とは?

根管治療は、歯の内部にある歯髄(神経や血管が含まれる部分)が感染したり、炎症を起こしたりした場合に行われる歯科治療法です。
この治療は、「神経を抜く治療」として知られています。
治療の過程では、まず感染した歯髄を取り除き、その後根管内を清掃し、消毒します。これにより、感染の拡大を防ぎ、歯を保存することが目的です。
むし歯治療と根管治療の違い

では、むし歯治療と根管治療はどのように異なるのでしょうか?
むし歯治療
むし歯の治療は、初期段階では患部を削り、詰め物や被せ物で修復することが基本です。
この段階では、歯の表面のエナメル質が影響を受けている場合が多く、痛みは少ないかもしれません。
しかし、むし歯が進行し、歯の内部にある歯髄(神経や血管が通っている部分)に達すると、根管治療が必要になることがあります。
むし歯の治療は、進行度に応じて異なりますが、早期発見・早期治療が重要です。 初期段階であれば簡単な処置で済みますが、放置することで治療が複雑になり、歯を失うリスクも高まります。定期的な歯科検診を受け、むし歯の予防に努めることが大切です。
根管治療
根管治療は、むし歯が進行して歯の内部にある歯髄(神経や血管が通っている部分)に達した場合に行われる治療法です。
この治療の目的は、感染した歯髄を除去し、歯を保存することにあります。
歯髄が細菌に感染すると、歯が痛んだり、顔が腫れたりすることがあり、放置するとさらに状態が悪化し、歯や骨を溶かしてしまう可能性があります。
根管治療は、歯を抜くことを避け、できるだけ自分の歯を保存しようとする治療法です。 現在の治療技術により、多くの場合で歯を救うことが可能とされていますが、治療後は歯が脆くなることがあるため、クラウンなどの被せ物をすることが推奨されます。 これにより、歯の強度を回復し、長期的な保存を目指します。
4つの治療法

根管治療には、下記のようにいくつかの治療法が存在します。
抜髄
抜髄は、根管治療の一環として行われる治療法で、歯の神経と呼ばれる歯髄(しずい)が炎症を起こしたり、感染したりした場合に、その歯髄を除去する処置を指します。
歯髄は、歯の中心部に位置し、神経線維と血管で構成されており、歯に栄養や水分を供給する重要な役割を担っています。
しかし、むし歯が進行し歯髄に達すると、歯髄は感染し、痛みや腫れなどの症状を引き起こすことがあります。
このような状態になった歯髄を放置すると、症状の悪化やさらなる感染の拡大が懸念されるため、抜髄によって感染源を取り除きます。
抜髄後、歯髄が存在していた根管内は清掃され、消毒された後、根充填材で充填されます。これにより、歯の内部を細菌から守り、歯を保存することが可能となります。
抜髄は、歯髄炎や根尖性歯周炎など、歯髄が死んでしまったり、感染が進行したりした場合に適用されます。
歯髄炎は、むし歯などによる持続的な刺激が原因で発生し、根尖性歯周炎は、歯髄が死んでしまった後に歯根の先端に膿が溜まる状態を指します。
これらの症状が見られる場合、抜髄による治療が必要となり、適切な処置を行うことで、歯を長期間保存することが目指されます。
感染根管治療
感染根管治療は、歯髄(神経や血管が通っている部分)が壊死したり、以前に行われた根管治療後に再び感染が起こったりした歯を対象とした治療法です。
この治療の主な目的は、根管内に繁殖した細菌を除去し、感染を根本から治療することにあります。
感染が進行し放置されると、細菌は顎の骨にまで達し、最終的には歯を失うことになりかねません。
治療の必要性がある症状としては、噛むと痛む、歯茎が腫れる、歯が揺れる、歯茎を押すと痛むなどが挙げられます。
これらの症状は、感染が歯髄だけでなく、歯を支える骨や歯周組織にも影響を及ぼしていることを示しています。
感染根管治療では、根管内の汚染物質を除去することが中心となります。
この汚染物質の除去は、専用の器具を用いた機械的洗浄と、次亜塩素酸ナトリウムなどの洗浄液を用いた化学的洗浄の両方を組み合わせて行われます。 治療後は、根管内を封鎖することで再感染を防ぎます。 治療中には、根管内の細菌が根管外へ押し出されることによる痛みや、患部に薬剤が触れることによる痛みが生じることがありますが、基本的には根管内の神経がないため、治療自体は痛みを伴わないことが多いとされています。
しかし、治療前から痛みや腫れがある場合には、麻酔を使用して治療が行われることもあります。
感染根管治療は、根管治療の中でも特に難易度が高く、治療期間も長くなりがちですが、適切に治療を行うことで、感染した歯を保存し、機能を回復させることが可能です。
再根管治療
再根管治療は、過去に根管治療を受けた歯に対して、再度行う治療法です。 この治療は、以前の根管治療後に細菌が再感染した場合や、根尖性歯周炎が再発した場合に必要となります。
再根管治療の目的は、根管内の細菌数を減らし、歯の健康を回復させることにあります。
再根管治療が必要となる症状には、噛むと痛む、歯茎を押すと痛む、膿が出るなどがあります。
しかし、患者さんが自覚症状を持たないことも多く、レントゲン検査で根尖性歯周炎が発見されることが多いとされています。
再根管治療が検討される状況には、重度の根尖性歯周炎の症状が確認できる場合、症状はないがレントゲンで根尖性歯周炎が確認できる場合、予防的な目的で根管治療の質を向上させる必要があります。
再根管治療を成功させるためには、無菌的な処置、徹底的な洗浄、そして緊密な封鎖が重要とされています。
なかでも、歯科用顕微鏡を使用した精密な作業が求められ、根管内の感染物質の除去や洗浄、充填材料による根管の封鎖など、高度な技術と設備が必要となります。
再根管治療は、根管治療の中でも難易度が高い治療とされ、患者さんの症状や歯の状態に応じて、慎重に計画され実施されます。
歯内療法
歯内療法外科は、非外科的根管治療だけでは解決できない症例に対して行われる、根管治療の一種です。
この治療法は、根尖部(歯の根の先端部分)の病変に直接アプローチするための外科手術を含みます。
主に、根尖病変が小さくならない場合、一度治療した歯の再治療、歯の土台による歯根破折リスクがある場合、根の先端が折れてしまっている場合、根管が複雑で非外科的治療が困難な場合、以前の根管治療で器具の破折片が残っている場合などに選択されます。
具体的な治療法としては、歯根端切除術と意図的再植術があります。
歯根端切除術は、根の先端部分を切除し、病変を取り除く手術です。
この際、マイクロスコープを使用して精密に作業を行い、必要に応じてMTA(ミネラルトリオキサイドアグリゲート)などの材料で根管を充填します。
一方、意図的再植術は、解剖学的な理由やほかの治療法で対応が難しい場合に選択され、歯を一度抜歯して外で治療を行った後、再び元の位置に戻す手術です。
これらの治療は、根尖部の病変を直接取り除くことで、非外科的治療では改善が見込めない症例に対して歯を保存する最後の手段となります。
根管治療費について

根管治療費には、保険診療の場合と自費診療の場合があります
保険診療
根管治療の保険診療費用は、治療する歯の根の本数によって異なります。
費用は一本の根の治療で、保険適用後の自己負担額で数千円となることが多く、具体的な金額は治療を行う歯科医院や治療の複雑さによって変わる可能性があります。
保険診療ではコストが抑えられますが、使用される材料や技術に一定の制約がある点を理解しておくことが重要です。
自費診療
自費診療の場合の根管治療費用は、使用する医療技術や材料によって大きく変動します。
高度な技術や新しい材料を使用することで、治療の成功率が上がり、仕上がりの質も期待できますが、それに伴い費用も高額になりがちです。
具体的な費用の範囲は数万円から50万円程度とされていますが、医院によって異なります。
この金額には、マイクロスコープや歯科用CTなどの先進的な治療設備の使用料も含まれる場合があります。
治療中・治療後の痛みと対処法

根管治療中や治療後に痛みが発生する場合があります。
治療に伴う痛み
根管治療において痛みが生じる原因は、治療過程での歯の神経への物理的な刺激や、治療後に歯や周囲の組織で起こる炎症反応によるものとされています。
治療中には局所麻酔が施されるため、痛みが少なくなるよう配慮されていますが、炎症による腫れや圧迫感が治療後に痛みとして感じられることがあります。
これらの症状は一時的なもので、適切なケアを行うことで時間とともに改善するとされています。
痛みの対処法
根管治療後の痛みに対処するには、まずは冷却で腫れを抑えること、そして医師の指示に従って痛み止めを適切に使用することが基本です。
また、治療部位を清潔に保ち、食事は柔らかいものを選ぶなど、歯をできるだけ負担から守る工夫も重要です。
痛みが予想以上に強い場合や長引く場合は、迅速に医師に相談しましょう。
歯科医院の選び方

根管治療は高い技術が必要とされるため、歯科医院選びも重要となってきます。
避けるべき歯科医院
根管治療を受ける際には、以下のような特徴を持つ歯医者を避けるべきです。
- 歯科用のCTを使用しない: 歯科用CTは、根管内の形態を3次元で把握するために必要です。
- ラバーダムを使用しない: ラバーダムは、治療中に細菌や唾液が根管内に入り込まないようにするために重要です。
- マイクロスコープを導入していない: マイクロスコープは、根管内を拡大し、明るく照らすことで、根管内の感染の状態や形態を確認しながら治療を行うために必要です。
- 滅菌などの衛生管理がしっかりしていない: 治療器具の滅菌やグローブの取り扱いなど、衛生管理が不十分な歯医者は避けるべきです。
- 外科治療に対応していない: 根管治療の再治療の場合など、外科的歯内療法が必要な場合があります。
これらのポイントを考慮に入れて、適切な歯医者を選ぶことが、根管治療の成功につながります。
歯科治療先を選ぶ際の重要ポイント
根管治療を受ける際に歯科医院を選ぶポイントはいくつかあります。
まず、根管治療は非常に難易度の高い治療であるため、医師の知識と技術が重要です。 そのため、医師の経験や専門性を確認することが大切です。
また、治療の精度を高めるためには最新の設備が整っていることも重要です。
具体的には、歯科用のCTやマイクロスコープの使用が挙げられます。
これらの設備は根管の形状を詳細に把握し、治療を正確に進めるために必要です。
さらに、衛生管理がしっかりと行われているかどうかもチェックポイントの一つです。
根管治療は細菌感染を防ぐための治療であるため、滅菌などの衛生管理が徹底されていることが求められます。
最後に、外科治療に対応しているかどうかも重要です。根管治療がうまくいかなかった場合には外科的な治療が必要になることもあるため、そのようなケースにも対応できる医院を選ぶことが望ましいです。
以上のポイントを踏まえて、自分の症状や状況に合った歯科医院を選ぶことが、根管治療の成功につながります。
まとめ
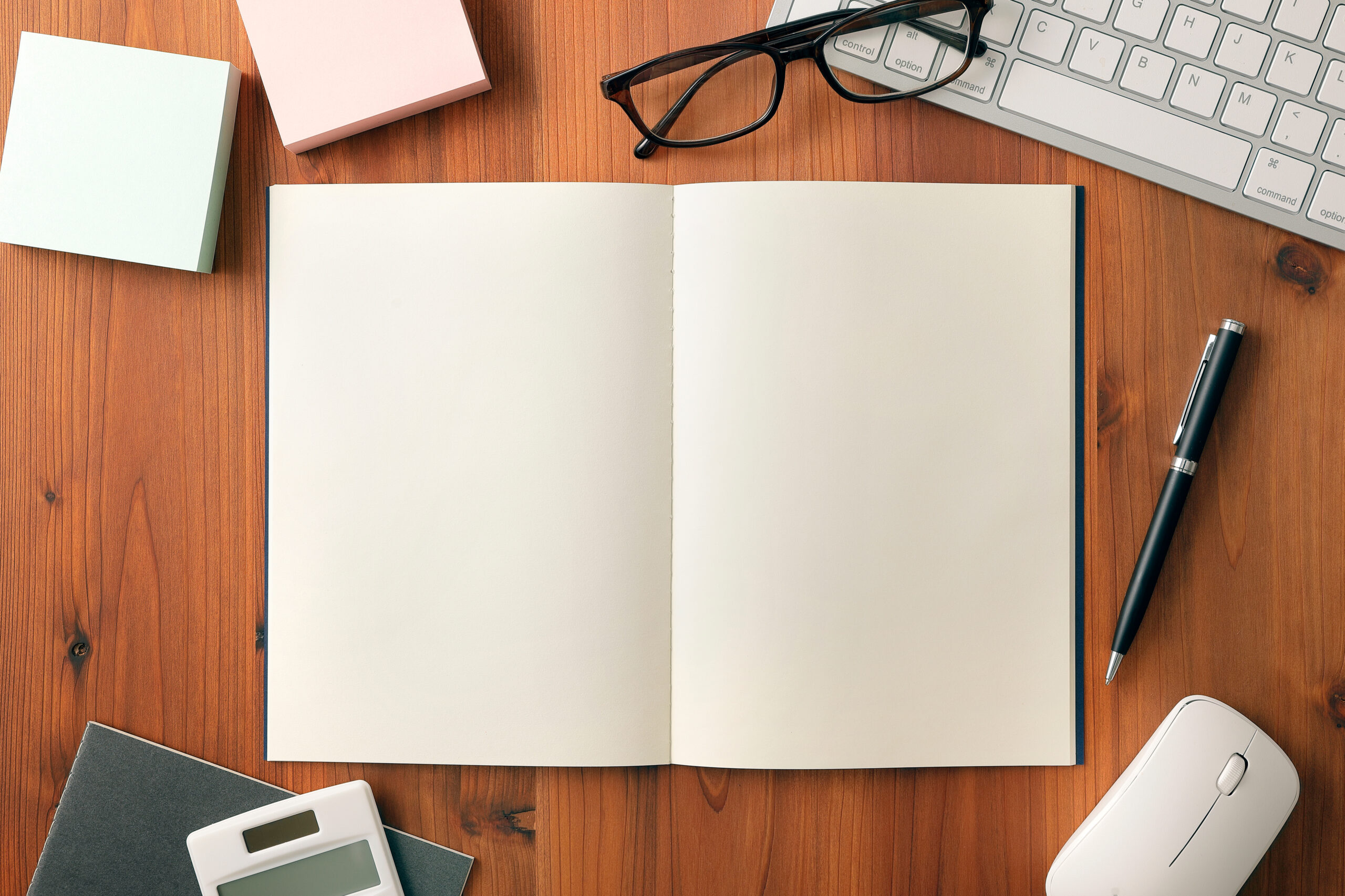
ここまで、根管治療でやってはいけないことについてご紹介しました。
根管治療でやってはいけないことについてまとめると、以下の通りです。
- 根管治療中に気を付けたいことは、治療を受けた歯が敏感になりやすいため、食事等で固いものに気を付ける
- 根管治療でトラブルが起きた場合は、医師の指示に従い、市販薬等を自己判断で使用しないこと
- 根管治療の歯科医院を選ぶ際、設備が不十分な場合や外科手術に対応をしていない歯科医院はおすすめできない
根管治療を成功させるためにも、まずは歯科医院選びから拘ってみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
