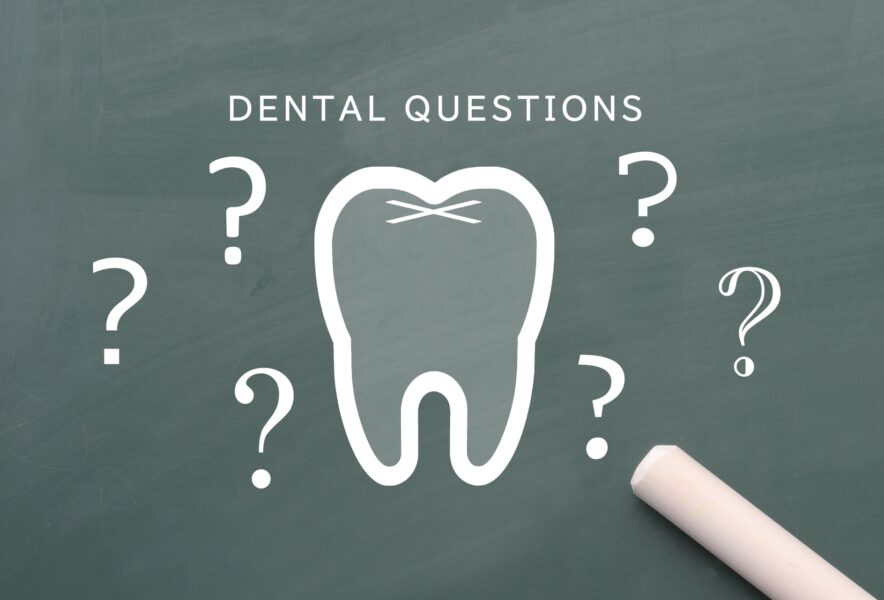根管治療は、細菌に感染した歯の根っこを消毒する処置ですが、1〜2回で終わることはまずありません。ケースによっては治療期間が数ヵ月に及ぶこともあるため、消毒が終わるまでにはどのくらいの回数、通わなければならないのか不安に感じている人もいることでしょう。そもそも根管治療ではどのようにして消毒するのかもわかりにくいものです。ここではそんな根管治療の消毒の方法や治療の流れ、消毒にかかる回数などを詳しく解説します。
根管治療とは
 はじめに、根管治療の目的と治療方法をかんたんに説明します。
はじめに、根管治療の目的と治療方法をかんたんに説明します。
根管治療の目的
根管治療の目的は、根管内の細菌感染を取り除くことです。殺菌作用のある薬剤を入れたり、専用の器材で病変を掻き出したりすることで、根管内を細菌に感染していない状態へと戻します。そうすることで初めて、歯を残す事が可能となるのです。
◎根管治療が必要となる症状
根管治療は、むし歯が進行して歯の神経まで感染が広がった場合、外傷などで歯の神経が死んでしまった場合、歯の根の先に膿の塊ができた場合などで必要となります。いずれもその状態を放置していると、歯そのものがダメになったり、周りの組織に感染が広がったりするため、根管内を消毒する必要性が出てきます。
根管治療の治療方法
私たちの歯は、頭の部分である歯冠(しかん)と根っこの部分である歯根の2つの部位から構成されています。歯冠は口腔内に露出している部位なので、むし歯になっても治療は比較的しやすいです。目に見えている部分の感染歯質を削り、詰め物・被せ物を装着すれば治療は完了します。
一方、歯根は歯茎の中に埋まっている部位であり、その中が細菌に感染してしまったら、穴をあけて根管口を露出させ、その中に消毒薬などを入れながらきれいに清掃しなければなりません。根管が複数ある場合は、一つひとつをていねいに消毒して、細菌のいない清潔な状態へと戻します。
根管治療の流れ
根管治療は、次の流れで進行します。ここではむし歯が進行して、歯の神経にまで感染が広がったC3を想定しています。
ステップ1:細菌に感染した歯質を削る
細菌に感染した歯質をドリルで削ります。その際、天蓋(てんがい)と呼ばれる歯質を削ることで、歯髄を取り除きやすくなります。
ステップ2:歯髄を抜く
クレンザーを始めとした専用の器具を使って、歯髄を抜き取ります。根管内に残った歯髄の断片は、根管治療を進めていく中で、ファイル等で除去していきます。
ステップ3:根管の拡大・形成
根管はとても細い構造をしているため、リーマーやファイルを使って拡大していく必要があります。清掃や充填をしやすいように、根管の形成も進めていきます。
ステップ4:根管の消毒・洗浄
根管内に、殺菌作用のある薬剤を入れて、洗浄します。この操作は1回だけ行うのではなく、ステップ3の根管形成や清掃の合間に、随時、行っていきます。リーマーやファイルで根管内を清掃していると、根管壁の削りカスなども生じることから、定期的に洗浄していく必要があるのです。
ステップ5:根管内に薬剤を充填する
根管内の清掃や消毒が完了したら、ガッタパーチャという樹脂製の材料とシーラーという殺菌作用のある薬剤を充填します。これらをすき間ができないくらい緊密に充填することで、むし歯の再発リスクを抑えられます。
ステップ6:歯の土台の築造と型取り
歯の土台にあたるコアを作って、歯型取りを行います。それを元に模型を作り、被せ物を設計・製作します。被せ物が完成するまでは、仮歯で過ごすことになります。
ステップ7:被せ物の装着
被せ物が完成したら、装着して、細かい調整を加えた上で治療が完了します。
根管治療における消毒の役割と回数
 根管治療には、必ず消毒という処置を伴います。むし歯治療では汚染された歯質を削るだけなのに、なぜ根管治療では消毒を繰り返し行う必要があるのか。その理由と消毒回数などを説明します。
根管治療には、必ず消毒という処置を伴います。むし歯治療では汚染された歯質を削るだけなのに、なぜ根管治療では消毒を繰り返し行う必要があるのか。その理由と消毒回数などを説明します。
消毒の役割と重要性
根管治療が必要になる歯の根管は、基本的に細菌で汚染されています。根管内に残った歯髄の断片も根管壁も感染が生じていることから、殺菌作用のある薬剤で消毒しなければならないのです。もちろん、根管治療でも歯冠部のむし歯のように、切削用のバーでガリガリと削れたら良いのですが、残念ながら根管はそれほど丈夫な構造ではありません。
そもそも根管は、髪の毛ほどの細さしかないため、地道な根管拡大・形成、消毒を繰り返していく他ないのです。複雑な根管の中に少しでも細菌の取り残しがあると、むし歯が再発してしまうことから、消毒は徹底する必要があります。
根管治療の通院間隔と消毒回数
根管治療は、1週間に1回の頻度で通院するケースが多いです。毎回の施術の最後には、殺菌作用が期待できる薬剤を根管内に設置して、細菌の数を減らしていきます。消毒回数は、前歯の根管治療で2〜3回、奥歯の場合は3〜4回程度です。つまり、1週間に1回の間隔で通院した場合は、1ヵ月くらいで消毒が終わることになります。ただし、感染根管治療や再根管治療の場合は、これ以上の消毒回数が必要になります。
ただし、根管内の状態が悪かったり、過去に根管治療を行った歯で再発が起こったりした場合は、もう少し長い治療期間を要することが多いです。また、これはあくまで消毒の回数であり、土台や被せ物を作る期間は含まれていない点に注意が必要です。
根管治療の消毒方法
 根管治療の消毒は、次に挙げる方法で行われます。
根管治療の消毒は、次に挙げる方法で行われます。
消毒剤を使用した消毒法
根管治療では、過酸化水素30%、ヨードチンキ、次亜塩素酸ナトリウム、クロルヘキシジン、EDTA(エチレン-ジアミン-テトラ-アセテート)、水酸化カルシウムといった消毒剤を使用します。それぞれ異なる効果や性質を備えた薬剤なので、必要に応じて使い分けていきます。どれかひとつということではなく、いくつかの薬剤を組み合わせるのが一般的です。
レーザーを用いた消毒法
近年は、根管治療の消毒に医療用レーザーを活用することもあります。例えば、歯科の分野でも広く使われている「ヤグ・レーザー」は、根管内の消毒に大きな力を発揮します。具体的には、根管内を洗浄している時にヤグ・レーザーを照射することで、微細な泡が発生して、根管内部の洗浄効果を高めます。その他の歯科治療と同様、レーザー照射によって強い痛みが生じることはありません。
消毒後の注意点とアフターケア
根管治療の消毒が終わった後には、いくつかの注意点があります。また、適切なアフターケアを施すことで、治療後のトラブルを避けやすくなるでしょう。
消毒後の注意点
 注意点1:患歯を刺激しない
注意点1:患歯を刺激しない
消毒した歯は、薬剤の影響もあって敏感になっています。そのため患歯を舌や指でいじったり、極端に辛いものや熱いものを口にしたりすると、痛みが生じるため十分な注意が必要です。
注意点2:消毒後しばらくは不快症状が続く
根管形成や消毒は、歯に対して大きな負担をかける処置なので、帰宅後、局所麻酔の効果が切れたらしばらく痛みなどの不快症状が続きます。どのくらいの痛みが生じるかはケースによって異なりますが、我慢できないほどの症状が現れた場合は、痛み止めを飲むなどして対処しましょう。痛み止めが効かないほどの症状は、何らかの異常が疑われるため、主治医に電話で相談することを推奨します。
注意点3:仮蓋が外れることがある
消毒後は毎回、仮蓋を詰めます。仮蓋は比較的やわらかい素材で作られており、歯質の接着も脆弱です。そのため何かの拍子に仮蓋が外れることがありますので、その際は適切に対処する必要があります。仮蓋の一部が欠けたくらいであれば、次の診療まで放置しておいても問題ありませんが、仮蓋の大部分、あるいは丸ごと外れた場合は、主治医に電話をして指示を仰ぎましょう。仮蓋が完全に外れている状態は、根管内がいつ汚染されてもおかしくありません。これまでの消毒が無駄になってしまうことから、早急に仮蓋をつけ直すなどの処置が必要となります。
注意点4:周りの歯や歯茎に異常が生じた
根管治療は、歯科医師が行う専門的な医療であり、安全性を十分に確保した上で実施されます。そのため健康被害が生じるリスクは極めて低いのですが、消毒薬が周りの歯や歯茎に接触して損傷してしまう可能性もゼロではありません。消毒後、帰宅してから周りの歯や歯茎に何らかの異常が認められた場合は、速やかに歯科医院へ連絡するようにしましょう。ケースによっては、迅速な対応が求められます。
消毒後の適切なアフターケア
消毒後に口腔衛生状態が不良になると、根管内への再感染が起こりやすくなります。その時点ではまだ最終的な被せ物を装着しておらず、根管内への細菌の侵入リスクが高くなっているのです。そのため消毒後は普段と同じように、場合によってはそれ以上ていねいに口腔ケアをする必要があります。
ただし、根管治療をしている歯に対して過剰ブラッシングをすると、歯に強い痛みが生じたり、仮蓋が外れたりする恐れがあることから、慎重なケアを心がけるようにしてください。また、食事の時は治療している歯で噛まないようにしましょう。
根管治療の消毒回数を減らす方法
 上述したように、根管治療は消毒だけでもそれなりの通院回数が必要となります。奥歯の根管治療であれば、消毒で1ヵ月程度の期間を要するのは、いろいろな面で負担が大きくなることでしょう。そこで気になるのが根管治療の消毒回数を減らす方法です。医療に近道はないように思えますが、実は根管治療というのは、保険診療と自費診療で消毒の回数や処置の精度が大きく変わることがあるのです。その他にも根管治療の消毒の回数を減らす方法がいくつかありますので、簡単に紹介します。
上述したように、根管治療は消毒だけでもそれなりの通院回数が必要となります。奥歯の根管治療であれば、消毒で1ヵ月程度の期間を要するのは、いろいろな面で負担が大きくなることでしょう。そこで気になるのが根管治療の消毒回数を減らす方法です。医療に近道はないように思えますが、実は根管治療というのは、保険診療と自費診療で消毒の回数や処置の精度が大きく変わることがあるのです。その他にも根管治療の消毒の回数を減らす方法がいくつかありますので、簡単に紹介します。
根管治療が必要な症状を早期に発見する
歯の神経への感染や歯髄壊死など、根管治療が必要となる症状を早期に発見することで、消毒回数を少なくできる場合があります。なぜなら根管治療は、根管内の状態が悪いほど、消毒にも回数がかかるからです。むし歯がエナメル質や象牙質にとどまっている段階で発見できれば、そもそも根管治療が不要となることもあります。
精密根管治療を受ける
ラバーダム防湿やマイクロスコープ、ニッケルチタンファイルなどを活用した精密根管治療なら、根管内の汚れを効率よく取り除けるため、消毒の回数を減らしやすいです。精密根管治療は自費診療となることから、1回の処置にかけられる時間が多いのも利点といえます。ケースによっては、1〜2回で消毒を終わらせることも可能です。
機器や設備が充実した歯科医院を選ぶ
歯科用CTが導入されている歯科医院なら、三次元的な画像診断が可能となるため、根管の本数や形態を正確に把握できます。その結果、病変の取り残しが少なくなり、根管を見落とすリスクも減少するため、消毒も早く終わることでしょう。最近は、一般の歯科医院でも歯科用CTを完備しているところが増えてきているので、精密な画像診断を受けやすい環境になりつつあります。逆に、先進の医療機器や医療設備が完備されていない歯科医院は、優先度を下げた方が良いといえるでしょう。
根管治療に強い歯科医師の治療を受ける
根管治療における消毒の回数は、歯科医師の知識・経験・技術によっても大きく変わります。当然ですが根管治療が下手な歯科医師が担当すれば、消毒の回数も多くなります。逆に根管治療が得意な歯科医師が担当すれば、効率よく汚れを取り除く方法や彎曲した根管への対処法なども知っていることから、処置がスムーズに進んで行きます。その結果として、消毒の回数も減少するのです。
◎歯内療法専門の歯科医師について
歯科医師にもそれぞれ専門分野があります。根管治療を始めとした歯の内部に対する処置は、総称して歯内療法(しないりょうほう)と呼ばれ、認定医や専門医も存在しています。ですから、根管治療に強い歯科医師を探す際には、歯内療法の資格を持っているかどうかがひとつの目安となります。
編集部まとめ
 このように、根管治療の消毒回数は、前歯で2〜3回、奥歯で3〜4回程度となっています。消毒は、過酸化水素や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤を使った方法が主流となっていますが、近年は医療用レーザーが活用される場面も増えてきています。根管治療では、先進の医療機器を活用することで、処置の精度を高めたり、消毒の回数を減らしたりすることが可能であることから、歯科医院選びは慎重に行う必要があります。とくに根管治療を担当する歯科医師の技術や経験は、消毒回数を減らす上で極めて重要となるため、カウンセリングの際にその点をきちんと確認することを推奨します。
このように、根管治療の消毒回数は、前歯で2〜3回、奥歯で3〜4回程度となっています。消毒は、過酸化水素や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤を使った方法が主流となっていますが、近年は医療用レーザーが活用される場面も増えてきています。根管治療では、先進の医療機器を活用することで、処置の精度を高めたり、消毒の回数を減らしたりすることが可能であることから、歯科医院選びは慎重に行う必要があります。とくに根管治療を担当する歯科医師の技術や経験は、消毒回数を減らす上で極めて重要となるため、カウンセリングの際にその点をきちんと確認することを推奨します。
参考文献