感染根管治療は、歯の根の周囲の組織まで細菌感染が拡大した際に行う治療です。
何もしなくても痛んだり歯肉や顎周囲が腫れたりしている場合は感染が広がっている可能性があり、早めの感染根管治療が必要です。
しかし、感染根管治療がどのような治療なのか、痛みの程度や治療期間などに不安や疑問を抱えている方もいるでしょう。
本記事では感染根管治療の流れや治療後の痛み・期間について解説するので、ぜひ参考にしてください。
根管治療の種類

根管治療は、歯の中の治療です。歯の中には、歯髄(しずい)と呼ばれる神経や毛細血管が集まっている組織、根管と呼ばれる管があります。
むし歯や外傷によって歯の中の組織が感染したり壊死したりした場合に行うのが、根管治療です。
感染や壊死した部分を放置しておくと、炎症が顎・顔・脳などにまで広がって重症化してしまう危険があります。
そのため、歯の中の感染・壊死した組織を根管治療によって速やかに取り除くことが大切です。
根管治療には、抜髄(ばつずい)と感染根管治療の2種類があります。以下では、それぞれの根管治療法について詳しく解説します。
抜髄
抜髄は、感染した歯髄を取り除く根管治療です。一般的に神経を抜くといわれるのは、抜髄のことです。
むし歯が進行して歯髄にまで到達したり歯髄が細菌感染を起こしたりすると、歯髄炎を発症します。
初期は冷たいものや熱いものがしみる程度ですが、進行すると痛みが強くなり、日常生活や睡眠に影響を及ぼすことも少なくありません。
歯髄炎は自然治癒しないため、抜髄をして感染している歯髄を取り除く必要があります。
抜髄では、歯髄と周辺の感染した組織を器具で削り取った後に消毒し、再感染を防ぐために詰め物をします。
感染根管治療

感染根管治療は、歯の根の周囲の組織にまで感染が広がった場合に行う根管治療です。
歯髄炎を放置すると細菌感染が歯の根の周囲まで広がり、歯髄が壊死して根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)となります。
また、過去に根管治療を行った部位で細菌が再繁殖し、根尖性歯周炎を引き起こすこともあります。
根尖性歯周炎になると、何もしなくても痛む・噛むと痛い・歯肉や顎周囲の腫れ・歯が浮く感覚などの症状が現れるでしょう。
重度になると、歯を支える骨の内部に膿が溜まって破壊されてしまいます。
根尖性歯周炎まで進行した場合は、感染根管治療で感染した組織や細菌などを取り除き、消毒を行ってさらなる感染拡大を防ぐ必要があります。
感染根管治療の流れ
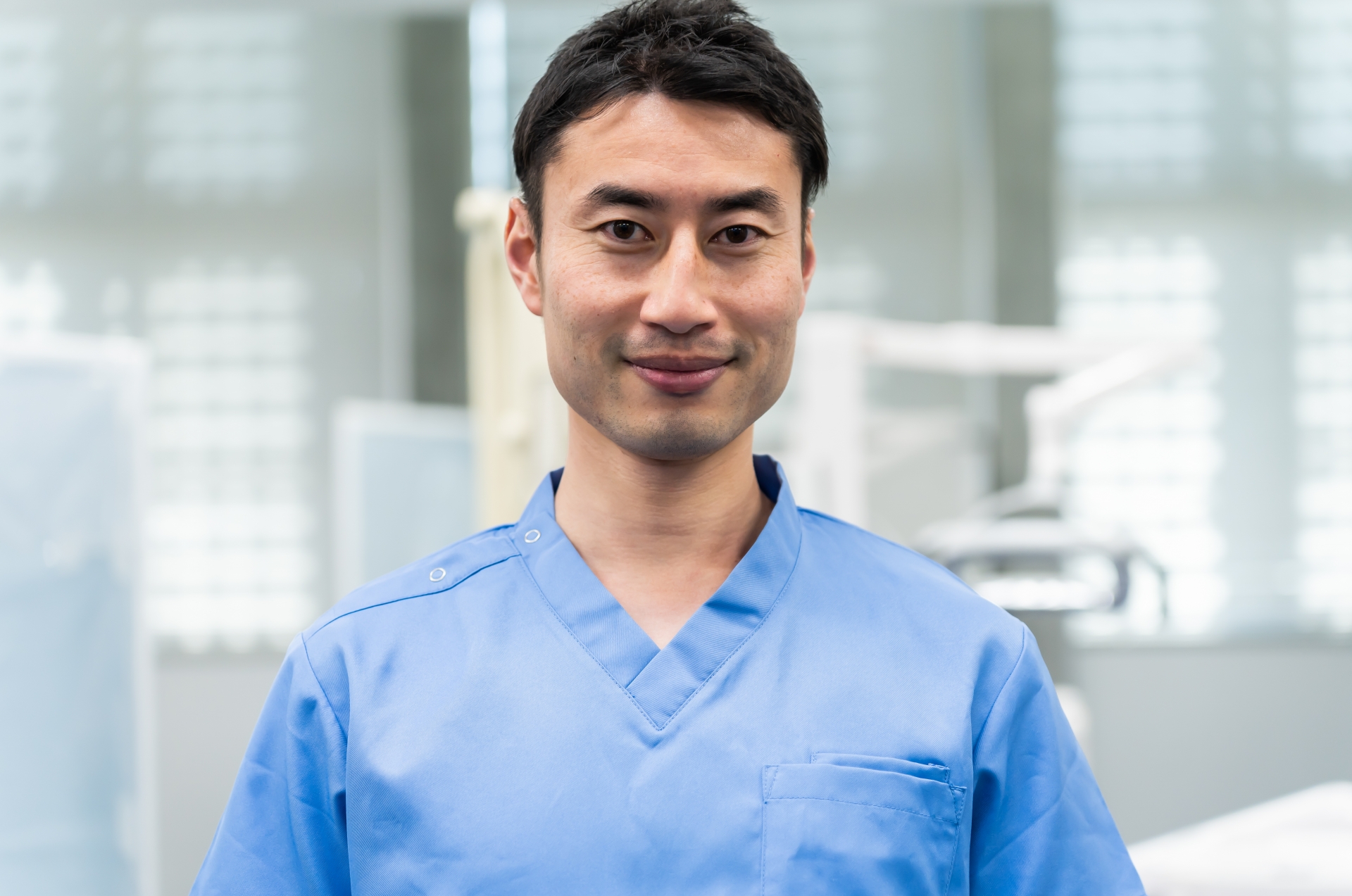
感染根管治療のポイントは、感染した組織や細菌をできるだけ除去して消毒し、再び感染しないよう細菌の侵入を防ぐことです。
では、感染根管治療ではどのような治療を行うのでしょうか。以下では、感染根管治療の流れを解説します。
麻酔をする
感染根管治療では歯の神経を取り除く必要があるので、痛みを感じにくくするためにまず麻酔をします。
しかし、歯の根は骨に埋まっている状態なので、直接麻酔を打つのは困難です。そのため、歯茎から麻酔液を注射して骨の内部に浸透させる浸潤麻酔法を行います。
また、麻酔が効きにくいとされる下の奥歯の治療を行う場合は、伝達麻酔法を加えることもあります。
伝達麻酔法は、脳と下顎をつなぐ神経の途中に麻酔薬を作用させ、お口の周りの広い範囲に麻酔効果を得られる方法です。麻酔が効いていることを確認したら、治療を始めます。
被せ物・土台を取り除く

次に、銀歯やセラミックなどの詰め物・被せ物・土台がある場合は取り除きます。
感染根管治療では歯の内部を確認しながら治療を行うため、被せ物の除去が必要です。
また、歯の中まで感染が広がっている段階では、詰め物・被せ物・土台にも細菌の影響が出ていることが少なくありません。
そのため、歯の神経を取り除く前に汚れている被せ物や土台を取り除きます。
感染した歯髄を取り除く
根管の長さを測定し、むし歯になった部分を削り取りながら歯に穴を開けていきます。
歯髄に届くところまで穴を開けたら、歯髄を専用の器具で取り除きます。その際、感染した歯髄を取り残さないよう注意が必要です。
感染した神経が残っていると、細菌が再繁殖して再発する可能性があります。
歯髄は歯の根の本数によって数本に枝分かれしているため、しっかり枝分かれを確認し感染した歯髄をすべて除去することが重要です。
ファイルで根管形成・清掃する
歯髄を取り除いたら、ファイルと呼ばれる針のような器具で根管形成と根管内の清掃を行います。
根管形成とは、根管内を広げて治療器具・薬剤・充填剤が根の先まで届くようにすることです。
歯髄を取り除いた後の根管内は細かったり蛇行したりしていて、根の先まで器具や薬剤が届きにくい状態です。そのため、根管形成で根管内をある程度削って広げます。
また、歯髄があった穴や根管の内壁は細菌の影響を受けているので、汚染された組織を少しずつ削りながら清掃してきれいにします。
根管内の洗浄・消毒をする

次に清掃してきれいになった根管内を薬剤で洗浄し、消毒します。
根管内にはファイルで削った削りかすや汚れが残っているので、次亜塩素酸ナトリウム(有機物を溶かす薬剤)やEDTA(無機物を溶かす薬剤)を使用して洗浄・消毒します。
汚れが残っていると再発の恐れがあるため、しっかり洗浄・消毒してできる限りきれいな状態にすることが重要です。通常は、数回にわたって洗浄・消毒します。
薬を充填する
きれいにした根管内に隙間なく薬を充填し、細菌の繁殖を防ぎます。
感染部分を取り除いた根管内には空間があるので、そこにガッタパーチャやMTAセメントと呼ばれる薬剤を充填してしっかり封鎖します。
この際、隙間があるとそこから細菌が繁殖する恐れがあるため、隙間なく充填することが大切です。
薬を充填した後は、レントゲン撮影をして薬が根の先まで届いているか・空気が入っていないかを確認します。
隙間が残っていた場合は、再発を防止するため薬の詰め直しが必要です。歯髄を取り除いた当日は消毒用の薬剤を入れて仮のふたをし、後日薬剤を充填するケースもあります。
土台の作製・被せ物を装着する
最後に土台を作製し、土台の上に被せ物を装着して歯を保護します。
根管治療をした後の歯は、構造が弱くなっていることが少なくありません。感染の程度によっては、歯を支える部分が大きく欠損していることもあります。
そのままの状態だときちんと噛めず歯として機能しないため、土台と被せ物を装着して歯を安定させ、歯の機能回復を図ることが大切です。
歯髄があった穴に金属やレジンなどの素材で土台を作製した後、レジンやセラミックでできた被せ物を装着して歯を保護します。
感染根管治療の精度を高めるための方法

感染根管治療は感染した歯の根や周辺の組織を残さず取り除き、洗浄・消毒して再感染を防ぐ治療です。
しかし、歯の根は奥まったところにあり、根管は複雑な形状をしていて肉眼での確認は難しいといわれています。
また、口腔内には無数の細菌が存在するため、できる限り無菌化した状態で根管治療を行い、根管内に新たに細菌が入り込まないようにすることが重要です。
感染根管治療の精度を高め成功率を上げるためには、ラバーダム防湿とマイクロスコープが有効とされています。
ラバーダム防湿
ラバーダム防湿は、患部以外をゴム製のシートで覆い細菌の侵入を防ぐ方法です。
感染根管治療の精度を高めるには、できる限り無菌化した状態で治療を行った方がよいといわれています。
根管治療中は、口腔内の細菌による感染のリスクがあります。
口腔内には無数の細菌が存在しており、根管治療中に唾液に混ざった細菌が根管内に入り込むと根管内で繁殖し、再感染を引き起こす可能性があるのです。
治療中にラバーダム防湿を行えば、患部に細菌を含んだ唾液が入り込むリスクを減らせます。
実際にラバーダム防湿をして、根管治療の成功率が上がった報告もあります。また、周囲の歯に感染した歯の細菌や削りかすが飛び散るのを防げるのもメリットです。
その他にも治療器具の誤飲を防げる、歯科医師が患者さんの唇や頬を抑えなくてよいため治療に専念できるメリットがあります。
マイクロスコープ
マイクロスコープは、20倍程度まで視野を拡大できる歯科用の顕微鏡です。患部を拡大して詳細を把握し、明るい視野で治療できるのが特徴です。
感染根管治療にマイクロスコープを使用すると、治療の精度向上と治療時間短縮につながるといわれています。
根管は歯の奥にあるため視野が暗く、根管内は狭くて複雑な形状をしているので肉眼で詳細を把握するのは困難です。
肉眼のみで根管治療をするとなると、勘と経験を頼りに治療を行うことになります。
感染根管治療では歯の中を詳しく把握し、感染部位を取り残さないように除去しなければ再発のリスクが高くなります。
治療の精度を高めるには、マイクロスコープで肉眼では見えない細かい部分まで適切に把握し、感染部位をしっかり除去することが重要です。
感染根管治療にかかる期間は?
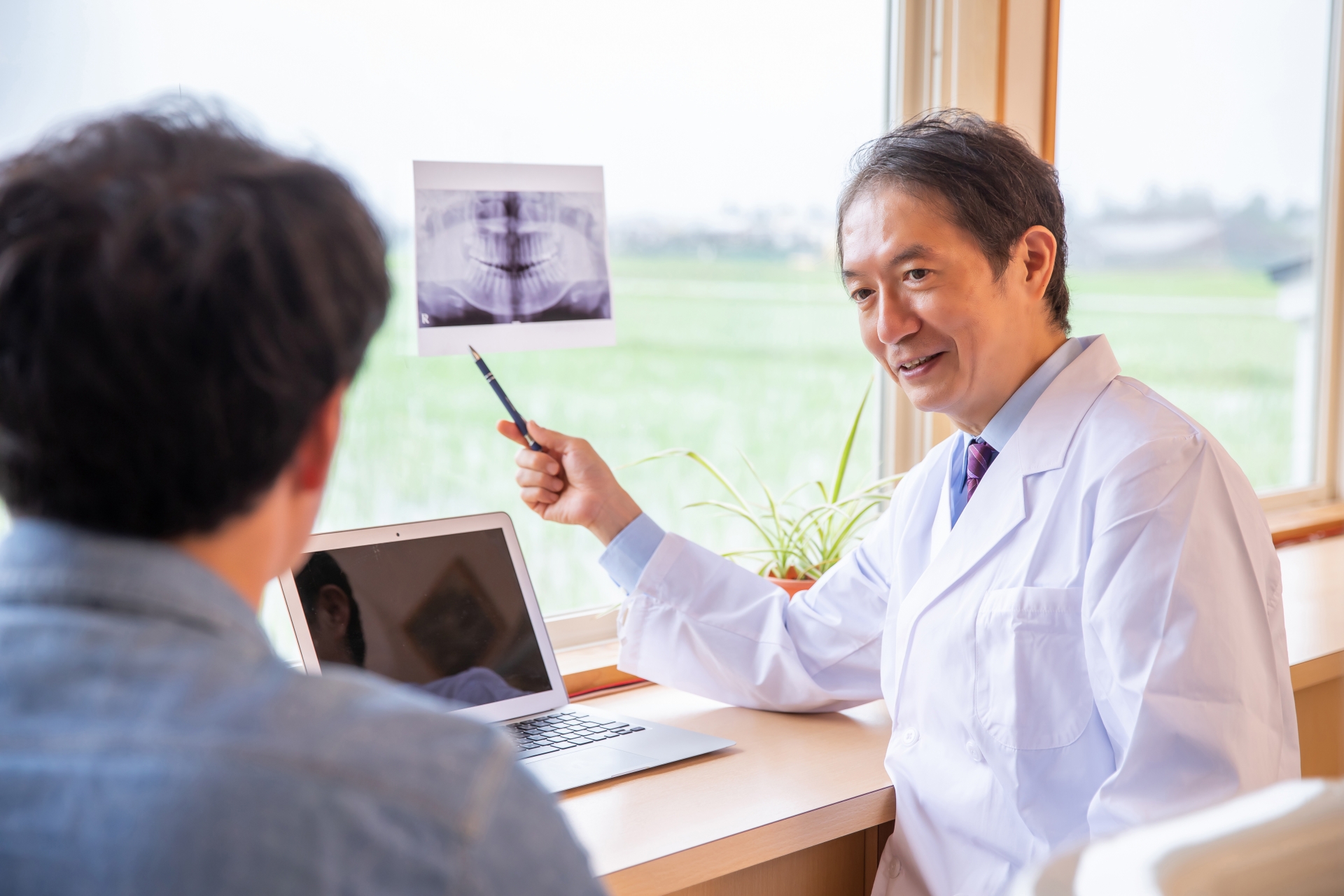
歯科治療は何度も通院しなくてはいけないイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。
感染根管治療はどのくらいの治療期間がかかるのか、気になる方もいるでしょう。
感染根管治療にかかる期間は、1ヵ月~1ヵ月半が目安です。通院回数の目安は2~3回で、1週間に1回程度で通院して消毒を行います。
ただし実際にかかる治療期間には個人差があり、長いと数ヵ月かかることもあるでしょう。
治療期間は、感染の進行度や歯髄の本数などによって変わります。感染根管治療では、感染部位を取り残さないよう慎重な治療が求められます。
また、一度の治療ですべての細菌を取り除くのは困難です。
そのため、ある程度の期間をかけて定期的に通院し、細菌の減少具合や症状の改善具合を確認しながら治療を進めます。
薬を充填するのは、十分細菌が減少してからです。
根管治療で歯の神経を取り除くと、痛みは感じにくくなります。痛みが少なくなったからといって治療を中断すると、歯を失うリスクが高まります。
感染根管治療は最後まで治療を継続し、感染部位をしっかり除去して患部を消毒することが大切です。
感染根管治療後に痛みはある?

感染根管治療後に痛みが出るのは、珍しいことではありません。治療後に軽度の痛みが生じる確率は30~40%といわれています。
感染根管治療後に痛みが生じる原因には、以下のようなものがあります。
- 歯の根の先から細菌が体内に入り込んだことによる免疫反応
- 歯の周囲の神経の一時的な痛み
- 薬を充填による痛み
- 歯周組織の炎症・膿
- 治療器具の刺激による歯の根の先端の炎症
- 再感染
根管治療後は、根管内の細菌が歯の根の先から体内に侵入し、細菌に対する免疫反応で痛みを生じることがあります。
痛みは軽度なケースが多いですが、まれに歯肉が腫れたり強い痛みが生じたりするケースもあるため注意しましょう。その場合は、洗浄・抗生物質・鎮痛剤で対処します。
また、根管治療では隙間ができないよう圧をかけて薬を充填するので、充填直後に痛みを感じることもあるでしょう。
痛みは通常は1週間程度、もしくは炎症が落ち着けば自然に治まります。痛みが気になるときは、処方された痛み止めを使用しましょう。
ただし、痛みが激しかったり長期的に続いたりする場合は、再感染の可能性があるため歯科医師への相談が必要です。
再感染が疑われるときはレントゲン撮影をして状態を確認し、必要に応じて再治療を行います。
感染根管の症状

ここまで感染根管治療の流れや精度を高める方法、治療期間や治療後の痛みについて解説しました。
では、どのような症状が出たら感染根管治療が必要なのでしょうか。
以下では感染根管の症状を慢性期・急性期に分けて解説するので、ぜひ受診の目安にしてください。
慢性期
慢性期には、以下のような症状が現れます。
- 疲労時・体調不良時に歯の付け根に鈍痛がある
- 歯茎を押すと違和感がある
- 噛むと違和感がある
- 歯茎の腫れを繰り返している
- 歯肉に小さい穴があって膿が出ている
- 走ると上の奥歯が痛む
むし歯が歯髄まで進行していても、炎症が慢性的な場合には上記のような軽度の症状に留まります。痛みも普段は感じず、体調が優れないときにのみ生じるのが特徴です。
急性期
急性期の症状には、以下のような特徴があります。
- 何もしていなくてもズキズキした強い痛みがある
- 痛み止めが効かない
- 痛みで眠れない
- 歯肉だけではなく顔・首・喉も腫れている
- 微熱や倦怠感がある
急性の炎症が起きている場合は、激しい痛みや広範囲の腫れなどの強い症状が現れます。
痛み止めが効かない程の痛みが生じるので、日常生活に影響が出るでしょう。
歯の周辺だけではなく、目の下や首まで腫れが広がり、喉が腫れてものをうまく飲み込めなくなることもあります。
まとめ

本記事では、感染根管治療の流れや治療期間、痛みについて解説しました。感染根管治療は、歯の奥にある根管にまで細菌感染が広がった場合に行う治療です。
神経を含め感染した歯の中の組織を取り除き、根管内をきれいにして消毒を行い、再感染を防ぎます。
根管が感染した際の症状は、慢性期・急性期で異なります。
根管が感染した状態を放置すると悪化して治療が長期化し、負担が大きくなるため注意が必要です。
歯や歯の周囲に異常を感じたら、早めに歯科医師に相談して対処しましょう。
参考文献
