「過去に根管治療を受けた歯が数年後に痛み始める」というようなケースは臨床の現場でよく見られます。日本の保険診療における根管治療の成功率は50%を下回っていることで有名ですが、「数年後に痛み始める」という再発リスクが高い点とも強く関連しています。本記事ではそんな再根管治療が必要となる原因と治療方法について、詳しく解説します。根管治療から数年後に痛みや違和感が生じた人は参考にしてみてください。
根管治療とは

- 根管治療の対象となる歯の疾患にはどのようなものがありますか?
- 歯髄炎、歯髄壊死(しずいえし)、根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)といった疾患では、根管治療が必要となります。
・歯髄炎
歯髄とは、歯の神経と血管からなる組織で、根管内に存在しています。その歯髄が細菌感染によって炎症を引き起こされると歯髄炎となり、抜髄(ばつずい)の必要性が出てきます。歯髄を抜いた後は根管内をきれいに清掃する処置を実施しなければなりません。細菌感染を伴わない単純性の歯髄炎では、消炎処置などで対応できることが多いです。歯髄炎だからといってすべてのケースで抜髄および根管治療が必要となるわけではないのです。・歯髄壊死
歯髄壊死とは、虫歯による細菌感染や外傷などが原因で歯髄が死んでしまった状態です。生活反応がないため、痛みを感じることもありません。壊死した歯髄を放置していると、感染の範囲が広がったり、歯が黒ずんできたりすることから、根管治療が必要となります。 ちなみに、歯髄に腐敗菌が作用して生活反応が失われた場合を歯髄壊疽(しずいえそ)といいます。歯髄が腐っている状態なので、強烈な腐敗臭を放ちます。そんな歯髄壊疽のケースでも根管治療が必須となります。・根尖性歯周炎
根尖性歯周炎とは、歯の根の先に膿の塊が生じる病気です。一般的には重症化した虫歯で現れる症状で、感染源は根管内にあることから、根管治療が必要となります。根管治療によって根管内の汚染物質がなくなったら、根尖部の膿や細菌も徐々に消失していきます。
- 根管治療とはどのような治療方法ですか?
- 根管治療は、リーマーやファイルといった針のような器具を使って、根管内の汚れを取り除く処置です。適宜、消毒薬を使いながら、根管内の洗浄も行います。初めての根管治療では、最初に抜髄をした上で、根管の拡大・形成を行い、清掃・消毒を進めていきます。今回のテーマである再根管治療では、被せ物や充填物の撤去など、初回の根管治療とは異なるプロセスが含まれる点に注意が必要です。詳細は後段で解説します。
- 根管治療の治療回数と治療期間について教えてください。
- 初めての根管治療は、2〜4回で処置が完了します。1週間に1回の頻度で通院した場合は、2〜4週間で根管治療が終わることでしょう。再根管治療の場合は、初回とは異なるプロセスが含まれているだけでなく、処置の難易度も高くなることから、4〜8回程度の通院が必要となります。毎週通院した場合は、1〜2ヵ月で根管治療が完了します。
根管治療を受けた数年後に痛みが生じる原因
- 根管治療後の痛みの一般的な原因について教えてください。
- 主な原因として、根管処置による刺激が挙げられます。根管治療では、金属製の器具を根管内に出し入れしたり、作用の強い消毒薬で洗浄したりすることから、歯や周囲の組織に強い刺激が加わります。根管治療の最中は麻酔が効いているため痛みを感じることはないのですが、帰宅後、麻酔が切れた後に痛みを感じやすくなります。そうした根管治療後の痛みは数日程度で治まります。
- 根管治療を受けた数年後に痛みが生じる原因にはどのようなものがありますか?
- 根管内への再感染、歯のひび割れや破損、隣接する歯の問題などが挙げられます。
・根管内への再感染
根管治療から数年後に痛みが生じた場合、第一に考えられるのは再感染です。根管内の虫歯の再発によって痛みが生じます。その原因としては、汚れの取り残しや未処置の根管の存在などが挙げられますが、「数年後」に痛みが生じていることから、被せ物の適合が悪くなったと考えた方が自然です。被せ物と歯質との間にすき間が生じ、そこから細菌が侵入した可能性が高いといえます。・歯のひび割れや破損
歯がひび割れたり、部分的に欠けたりした場合もそのすき間から細菌の侵入が起こります。根管治療を行った歯は、健全な歯よりも脆くなる点に注意しなければなりません。・隣接する歯の問題
隣の歯が虫歯になったり、噛み合わせに異常があったりすると、根管治療を行った歯にも悪影響が及ぶことがあります。具体的には、隣の歯から虫歯がうつる、根管治療をした歯が強く噛むようになることで、痛みや腫れを引き起こします。
根管治療を受けた数年後に痛みが生じた際の治療方法
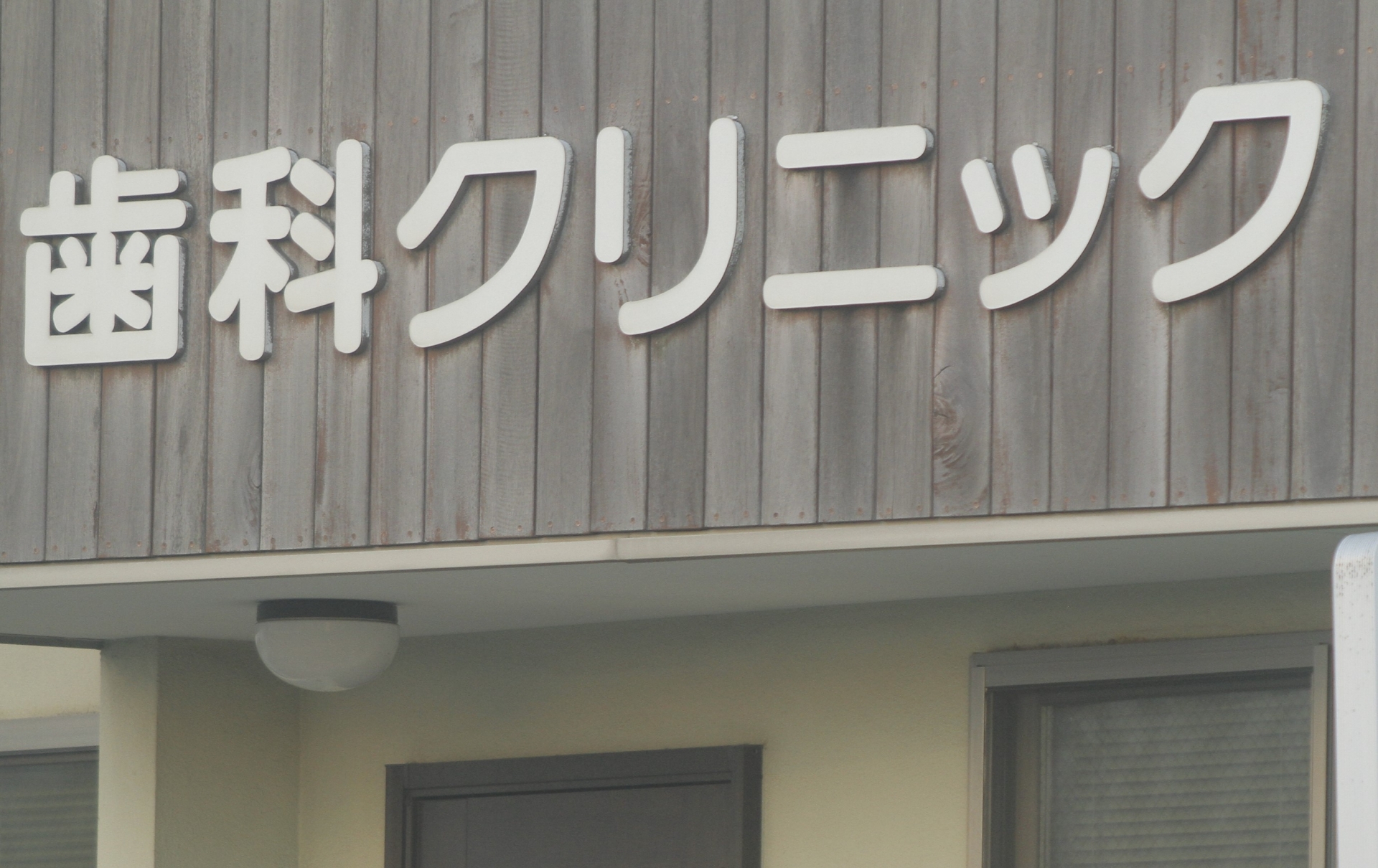
- 根管治療を受けた数年後に痛みが生じた際の治療方法にはどのようなものがありますか?
- 再根管治療、歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)、再植術、抜歯という4つの選択肢が用意されています。それぞれの特徴は以下の通りです。
・再根管治療
治療済みの歯に対して再び根管治療を行う方法です。日本では根管治療後に再発するケースが多いため、再根管治療も広く一般的に行われています。・歯根端切除術
歯の根っこの先を外科的に切除する方法です。・再植術
歯を丸ごと抜いてから、手元で根管治療を行った上で、元の位置へと戻す方法です。・抜歯
ここまで紹介した方法で痛みや腫れ、膿の排出が改善されないと診断された場合は、抜歯が適応されます。歯を抜いた後は、ブリッジや入れ歯、インプラントで欠損部を補います。抜歯では、天然歯を丸ごと1本失うことになるため、ネガティブなイメージを持っている人の方が多いかもしれませんが、歯の根の病気に関しては、無理に保存した方が悪い結果を招くことも少なくありません。もちろん、歯根端切除術や再植術のような高度な外科的歯内療法を適切に行える歯科医師が見つかればそれに越したことはありません。けれども、現実的に患歯を抜いて補綴装置を装着した方が予後も良くなるケースが少なくないことも知っておくことが大切です。
- 再根管治療とはどのような治療方法ですか?
- 文字通り根管治療を再び行う方法です。過去の治療で入れた被せ物と土台、根管内の充填物は完全に撤去します。その上で根管内を清掃し、無菌化が達成されたら再び根管充填を行います。この時、注意が必要なのが「なぜ再発したのか」ということです。根管への処置が不十分で病変の取り残しがあった場合は、根管の彎曲や枝分かれ、見落としている根管の存在を正確に把握する必要があります。また、一度、根管治療を実施した歯は、歯質が脆くなっていることから、リーミングやファイリングを慎重に行わなければなりません。初めての根管治療よりも期間が長くなる点も理解しておく必要があります。
- 歯根端切除術とはどのような治療方法ですか?
- 歯根の先が強く彎曲していたり、清掃することが難しい枝分かれが存在していたりする場合は、標準的な再根管治療ではなく、歯の根の先とその周囲の病変を外科的に切除します。感染源をきれいに取り除くことができたら、歯根の先から根管充填を行います。歯根端切除術は外科的歯内療法の一種であるため、専門的な知識や技術を有した歯科医師を探すことが重要となります。
- 再植術とはどのような治療方法ですか?
- 口腔からのアプローチでは根管内の病変を適切に取り除けないと判断した場合に適応される治療法です。歯を抜いて根管処置を施し、充填まで行った上で元の位置へと戻します。抜歯をして再植するというプロセスはさまざまなリスクを伴うため、適応されるケースは一部に限られます。また、再植術をはじめとした外科的歯内療法に長けた歯科医師でなければ、成功させるのは難しいといえるでしょう。
編集部まとめ
このように、根管治療を受けた歯が数年後に痛み始めた場合は、再感染の可能性、歯のひび割れや破損、隣接する歯の問題などが疑われます。いずれも深刻な異常なので、放置はせず適切な治療を受ける必要があります。治療法の選択肢としては、再根管治療、歯根端切除術 、再植術、抜歯の4つが挙げられ、それぞれ適応症や治療手順、難易度も大きく異なる点に注意が必要です。
参考文献
