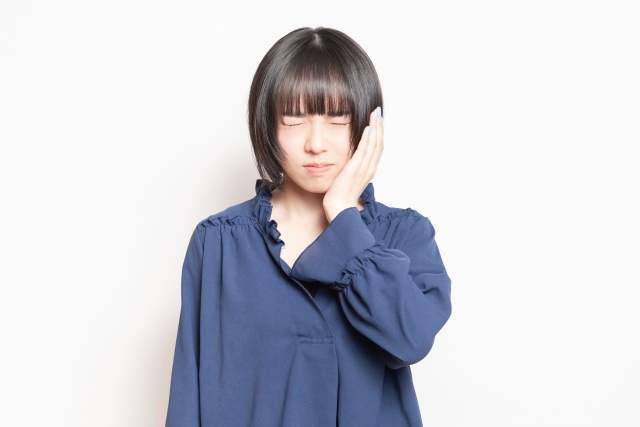根管治療は歯の内部にある神経を処置する治療であることから、痛みについて心配という方も多いのではないでしょうか。
根管治療は通常麻酔をして痛みを抑えますが、場合によっては麻酔を行わないこともあります。
この記事では、根管治療における痛みや、歯科治療の痛みを抑える方法などについて解説します。
根管治療とは

歯の内部には、身体から栄養を受け取るための血管や神経が存在していて、歯の根っこ部分にある、血管や神経が通る細い管のような部分を根管と呼びます。
一般的に、根管治療はこの神経や血管を除去し、歯の内部の徹底的な洗浄と殺菌によって、歯の内部にまで及んだ細菌の感染を取り除く治療を指します。
根管治療が必要になるケース
根管治療は、むし歯が進行して歯の神経部分にまで到達してしまった場合に行われる治療です。
歯の頭(歯冠)は外側からエナメル質、象牙質、歯髄という3つの層で構成されていて、このうち歯髄と呼ばれる内側の層が、歯の神経などが集まっている場所です。 むし歯が歯髄にまで到達すると強い痛みを感じるようになりますが、この痛みは神経が細菌に感染して炎症を起こしているものです。
痛みを取り除くためには神経を除去する必要があり、根管治療が行われます。
根管治療を受けるメリット
根管治療を受ける特に大きなメリットは、重度に進行してしまったむし歯でも、歯を抜かずに残して治療を行えることです。
根管治療は神経の除去は行いますが、歯そのものは薬剤を詰めて残しておくことができます。
例え神経を除去したとしても、天然の歯を残して被せ物などで噛み合わせを補った方が、入れ歯などの治療よりも自然な噛み心地を実現しやすいですし、顎の骨が減少してしまうリスクなども予防できるといえます。
根管治療を受けるデメリット
根管治療におけるデメリットの一つが、治療によって歯の強度が落ちてしまう可能性がある点です。
根管はとても細い管であり、そのままの状態では細菌の感染部位を隅々まで除去する対応が困難です。そこで、根管治療を行う際には、根管拡大という根管部分を広げる処置が行われます。根管拡大はしっかりとした治療を行うために必要であるものの、内部の空洞が広がって歯の強度が低下し、強い力が加わった時に歯の破折などが起こりやすくなる場合があります。 また、根管治療は歯の神経を除去するため、歯が痛みを感じにくくなり、むし歯が再発してしまった場合に気が付きにくくなる点もデメリットとして挙げられます。
歯の神経がないと、むし歯が深くまで進行していても気が付かなくなってしまい、気が付いたら抜歯が必要など手遅れの状態になるケースも考えられます。 そして、根管治療は再発、再治療になる場合がある点も、デメリットといえます。
むし歯の治療においては、細菌の感染を除去しきれずに残ってしまうと、そこから再度感染が広がってしまうケースがあります。しかし歯の内部という、とても繊細な部位の治療を行う根管治療は、細菌を除去しきれずに残ってしまいやすいという特徴があります。
根管治療は成功率が高い治療とはいえず、場合によっては何度も治療を繰り返し、最終的に抜歯が必要になってしまうという可能性もあり得ます。 根管治療の成功率を高めるためには、マイクロスコープを使用した精密な診療などを受けることが一つの手段といえますが、こうした治療は保険適用ではないため、成功率の高い治療を受けようとすると、治療費用が高くなってしまいやすいという点も、根管治療のデメリットであると考えられます。
根管治療の流れ
根管治療は通常、複数回の通院が必要になります。 まずはじめはしっかりと検査を行ってむし歯の状態を確認し、細菌に感染している部位を歯科用のドリルなどで削っていくことからスタートします。
歯髄部分が露出したら、細菌に感染している歯の頭の部分(冠部)歯髄を取り除きます。次にファイルと呼ばれる専用の器具などで根管内を拡大、洗浄し、感染部位を除去していきます。
感染部位の除去が終わったら、清掃を行った空洞に薬剤を詰めて蓋をして、1度目の治療が完了します。 その状態で数日間が経過したら、炎症などが生じていないことを確認します。
このときに歯髄症状が確認されたら、内部の感染を徹底的に除去する再治療が必要になります。
炎症などのトラブルがなく、感染部位の除去が完了できているようであれば、残っている歯を土台に整形して、上から被せ物(人工の歯)を装着する治療に進みます。
根管治療での腫れや痛みについて

根管治療の処置を行っている間や治療後に生じる痛み、そして腫れがどのようなものかを解説します。
根管治療の処置中の痛み
根管治療は、痛みを感じる歯の神経そのものを除去してしまう治療です。神経に触れることから強い刺激が心配になるかもしれませんが、実際には麻酔下で治療を行うため、処置中に痛みを感じることは少ないといえます。
ただし、痛みを防ぐための麻酔を注射する際には、チクッとした痛みが生じる可能性があります。
なお、場合によっては治療中に痛みや不快感を覚える可能性がありますが、その際は歯科医師に伝えれば麻酔の追加など適切な対応を受けることができます。
根管治療中に生じる腫れや痛みの原因
根管治療を行うと、その刺激によって治療部位の周囲に炎症が発生し、腫れや痛みが生じてしまう可能性があります。
また、治療によって傷ついた組織を修復するための免疫反応によって腫れる場合もあります。
こうした腫れや痛みは一時的なものであり、身体が回復していく過程で表れるものなので、心配はいりません。通常は治療から数日が経過すれば症状も落ち着いていきます。
治療直後には痛みが出やすい時期もありますが、処方される痛み止めなどを服用すれば軽減可能です。 一方、根管治療でむし歯の感染や神経を除去しきれなかった場合は、再感染によって強い炎症が出ることがあります。
また、感染が根尖という歯の根の先まで広がってしまっている場合には、この部分に炎症が残り、腫れを引き起こすことがあります。
このようなケースにおいては、時間経過とともに症状が悪化してしまう可能性があり、根管治療のやりなおしや、外科的な治療などが必要になるケースもあります。
根管治療後に痛みが生じるケース
根管治療が終わり、被せ物などの処置まで完了した後に痛みが生じるケースとしては、歯の破折や噛み合わせの不調などが考えられます。 根管治療を行うと根管拡大などによって歯が脆くなりやすいため、治療後に強い力で噛むなどすると、歯が割れたり、ひびが入ったりしてしまう可能性があります。
根管治療を行った歯には神経がないため痛みを感じませんが、割れた歯によって歯肉が傷ついたり、割れた部分に感染が生じて周囲に炎症を引き起こしたりすると、腫れや痛みにつながります。 噛み合わせの不調は、作製した補綴物などの調整が適切ではなかった場合に、一部の歯に強い力がかかりやすくなってしまうなどの変化が起きて痛みが生じるものです。
痛みを解消するためには、補綴物の作り直しや調整を行い、適切な噛み合わせにする必要があります。
なお、被せ物をした直後の数日間は新しい歯にまだ慣れていないことから、歯が浮いたような感覚になるなどの違和感が生じる可能性があります。この場合は時間経過とともに新しい歯に慣れていきます。
根管治療における麻酔について

根管治療は、歯の状態によって麻酔を行うケースと麻酔をしないケースなどがあります。
根管治療における麻酔の役割などについて解説します。
根管治療における麻酔の役割
根管治療は、歯の神経などを除去し、内部の感染を取り除く治療です。
神経に触れると強い刺激が生じるため、適切に治療を行うためには、麻酔で痛みを抑えながら治療を進める必要があります。
根管治療で麻酔を使用するケース
根管治療は、基本的には麻酔を使用して治療を行います。
多くの場合は局所麻酔で、歯の神経に触れても痛みが生じないようにしたうえで、神経を除去していきます。
また、治療に対する恐怖心が強い方などの場合は、笑気麻酔や静脈麻酔を使用することもあります。
根管治療で麻酔を使用しないケース
治療を行う歯の神経がすでに死んでいる場合、歯の治療で痛みが生じることがないため、麻酔を使用せずに治療を行う場合もあります。 また、すでに歯の神経が除去されていることがわかっている場合も、麻酔なしで治療をする可能性があります。
例えば、根管治療を行った後にむし歯が再発し、再根管治療を行うケースがこれに該当します。1回目の根管治療で神経が取り除かれているため、再治療の際には麻酔なしで治療を行う場合があります。
神経が死んでいても麻酔は必要?
むし歯が神経に感染しても治療をせずに放置していると、あるときに痛みがなくなる場合があります。これは神経が死んで痛みを感じなくなったためで、神経が死んでいれば麻酔をしなくても、歯の治療で痛みを感じなくなります。
しかし、この場合でも歯のすべての神経が死んでいるとは限らず、感染が広がらずに残っている神経がある可能性もあります。もしも神経が残っていたら、麻酔をしないで治療をすると強い痛みが生じることになってしまいます。
そのため、根管治療を行う際にはたとえ神経が死んでいたとしても、痛みを感じることがないかの検査をきちんと行い、場合によっては麻酔をしてから治療をする必要があります。
歯の治療における麻酔注射の痛みを軽減する方法

歯の治療は麻酔で痛みを抑えることができますが、麻酔注射そのものの痛みが怖いという方もいるのではないでしょうか。
近年は歯科医院も麻酔注射の痛みを抑えるためさまざまな工夫を取り入れていて、痛みを抑えた治療を受けることができます。
歯科医院で行われている、麻酔注射の痛みを軽減する方法を紹介します。
表面麻酔を利用する
表面麻酔は、塗るまたは貼る麻酔薬によって痛みを軽減するためのものです。麻酔注射を刺す場所にあらかじめ表面麻酔を施すことで、注射の際の痛みを軽減できます。
細い注射針を使う
麻酔注射に使用する針が細いと、注射の痛みを感じにくくなります。
麻酔薬の温度を調整する
麻酔注射を行う際、薬剤の温度と体温の差が大きいと麻酔薬が注入される刺激を感じやすくなります。
麻酔薬を体温程度に温めることで、注射による刺激を軽減し、痛みを抑えることが可能です。
電動麻酔器を利用する
麻酔薬を、刺激を感じにくい一定の速度で注入できる電動麻酔器の使用も、麻酔の痛みを軽減するための工夫の一つです。
機械制御で注射を行うため、安定感のある注射が期待できます。
根管治療後に腫れや痛みが生じた場合の対処法

根管治療を受けた後に強い腫れや痛みが生じた場合、または腫れなどがなかなか引かない場合は、下記のような対処を行いましょう。
早めに歯科医院に相談する
腫れや痛みに限らず、治療中に何かトラブルが生じた場合、放置していると時間経過とともに症状が悪化してしまう可能性があります。
また、自己判断での対応は、余計なトラブルを誘発してしまう可能性もあるため、何よりもまず早めに歯科医院に相談することが大切です。
適度に冷やす
根管治療後の炎症による腫れや痛みは、患部を冷却することで一時的に和らげることができますので、保冷剤を清潔なタオルでくるんだものなどを使って冷やすとよいでしょう。
その逆に、お風呂に入るなど患部を温める行為は炎症を広げてしまう可能性があるため控えましょう。
痛み止めを服用する
根管治療の際には痛み止めが処方されます。まずは処方された内服薬を飲んで痛みの対策をしましょう。
通常は処方された痛み止めがなくなる頃には強い痛みが軽減しますが、それでも痛みが続く場合は市販の痛み止めを服用しても大丈夫です。
ただし、あまりにも痛みが続く場合は何かトラブルが生じている可能性がありますので、やはり早めに歯科医院を受診するようにしましょう。
根管治療の痛みを防ぐためにできること

根管治療の痛みを防ぐためには、下記のポイントに注意しましょう。
設備が整った歯科医院で治療を受ける
お口の状態を詳しく検査できる歯科用CTや、精密な治療を可能にするマイクロスコープなど、先進的な設備が整った歯科医院で治療を受けることは、根管治療のトラブルを避けるための重要なポイントです。
注意点として、設備が充実している歯科医院で治療を受けても、保険適用では先進的な設備が利用できない場合があります。
自分に合った治療を受けたいという方は、保険診療に制限せず、自費診療での治療も検討してみるとよいでしょう。
痛みに配慮した治療を行っている歯科医院を選ぶ
麻酔の痛みを軽減するための対応など、痛みに配慮した治療を行っている歯科医院を選ぶことは、根管治療における痛みを防ぐためのポイントの一つです。
歯科医師の指示を守る
根管治療を受けた後の過ごし方やケアが不適切な場合、腫れや痛みが強くなってしまう可能性があります。
治療を受ける際は、薬の服用や生活上の注意点、歯磨きなどのケア方法といった指示が行われますので、しっかりと指示を守って治療に取り組むようにしましょう。
治療を途中でやめない
根管治療は、何度か通院を繰り返す必要が生じる場合がある治療です。
治療を自己判断で中断してしまうと、むし歯の再感染や感染の拡大などが生じて炎症が強まり、痛みにつながってしまう可能性があります。
治療内容に疑問が生じたらまずは主治医に相談し、治療が完了するまでしっかりと治療を続けるようにしましょう。
まとめ

根管治療は麻酔下で行うことが一般的ですが、再根管治療など神経がないことがわかっている場合は麻酔なしで治療を行う場合もあります。
ただし、麻酔が必要かどうかはしっかりとした診察のうえで判断する必要があり、一見歯の神経が死んでいるようなケースでも、場合によっては麻酔が必要になります。
クリニックによっては根管治療の痛みを軽減するため、麻酔方法の工夫などさまざまな取り組みが行われていますので、痛みを抑えた治療を受けたい方は、痛みや身体への負担を考えた治療を心がけている歯科医院を選んでみてはいかがでしょうか。
参考文献