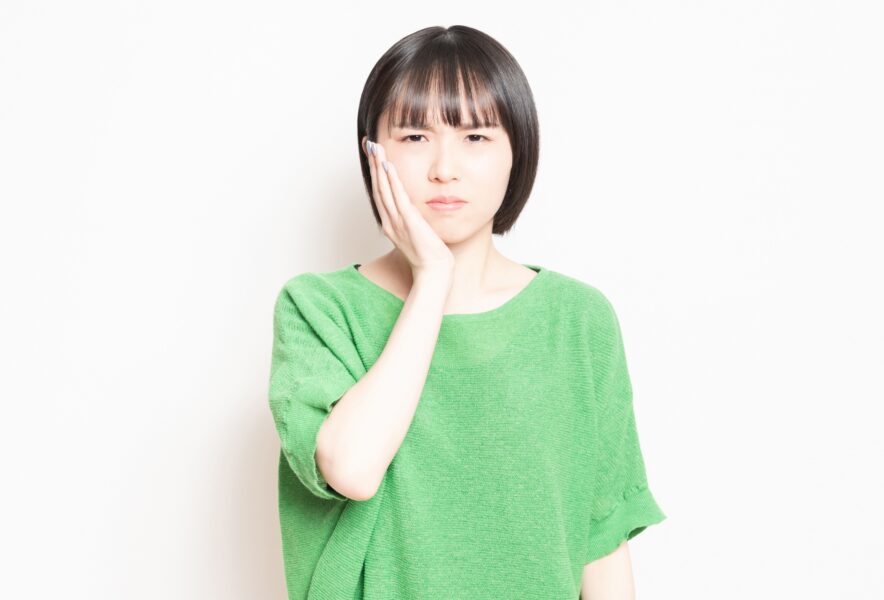根管治療は、歯の内部にある歯髄が感染・壊死した場合に行う治療です。しかし、根管治療後には、感染が再発する場合もあります。
今回の記事では、こうした根管治療の失敗について、原因・症状・治療法・抜歯の必要性などを解説します。
記事の後半では、根管治療を中断するとどのようなことが起こるのか、根管治療で失敗しにくい歯科選びのポイントも解説するので併せて参考にしてください。
根管治療の失敗は抜歯が必要になる?

人の歯は、食べ物や唾液に触れる部分がエナメル質という硬い層に覆われています。その中には象牙質の層があり、さらに中心にあるのが歯髄です。
歯髄は、歯茎の中に埋まっている歯根部へ伸び、歯の最下部である根尖(こんせん)までつながる組織です。
根尖には歯髄に含まれる神経・血管が顎骨の中までつながるように、根尖孔(こんせんこう)という小さな穴が開いています。
そのため、歯髄の感染・壊死などを放置すれば、根尖孔を通って顎骨まで広がる可能性があります。
むし歯・外傷などにより歯髄が感染や壊死を起こした場合に、感染を広げないために行われてきた方法が抜歯です。
しかし、抜歯した部分を人工物で補っても、自分の歯を失えば歯や口腔の機能は低下するといわれています。
そこで現在は、歯髄をきれいに取り除き、その周りにある象牙質・エナメル質を残す根管治療という治療方法も行われるようになりました。
ただし、1度目に行った根管治療が失敗して感染が再発する場合があるため、根管治療を行った後も定期的な受診や日頃のケアが重要です。
もし根管治療が失敗した場合には再根管治療を試みますが、歯・顎・歯茎などの状態から根管治療が難しいと判断されると抜歯になる可能性があります。
根管治療が失敗する原因

根管治療の失敗は、状態によっては抜歯につながる場合があります。では、根管治療が失敗するのはなぜなのでしょうか。4つの原因を詳しく解説していきます。
感染組織が多く残っている
感染・壊死を起こした歯髄を取り除くことを、神経を抜くと表現することがあります。しかし、歯髄は草の根のように上部を引っ張ればきれいに抜けるものではありません。
細い器具を使用して、取り残しがないか歯科医師が確認しながら時間をかけて取り除く作業です。
そのため、一見するとすべての感染組織を取り除いたようにみえても、歯根の奥に感染組織が残っている場合があります。
この状態のまま根管内の消毒・充填・被せ物などを行っても、密閉した歯の内部で細菌が増殖し再発につながりやすくなります。
根管充塡や被せ物に隙間がある

感染組織を十分に取り除いた後は、新たな細菌が外から入り込んだり、微かに残った細菌が根管内で再び増殖したりするのを防ぐために根管充填・被せ物をします。
しかし、この密閉が不十分であれば、口腔内の細菌が被せ物の隙間から入り込む可能性があります。また、不十分な根管充填による微細な隙間は細菌の温床です。
こうした状況では、一度殺菌を行った根管内で再び細菌が増殖し、炎症・組織の壊死などを起こすでしょう。
根管の壁に穴が開いている
根管の形状にはさまざまなパターンがあり、時には根管が歯の表面付近を通っている場合があります。
そのため、細い根管から歯髄を除去する過程で、人工穿孔が起こることがあります。人工穿孔とは、根管内を削って拡大することで歯に小さな穴が開くことです。
もし穴が開いた場合でも、穿孔に気付いた時点ですぐに、適切に穴をふさげば大きな問題はありません。
しかし、穿孔に気付かず穴が開いたままの状態で根管治療を終えれば、その穴から新たに細菌が入り込み根管内で増殖する可能性があります。
折れた治療器具が根管に残っている
根管から歯髄を取り除くための器具は先端が非常に細く、力を加えすぎたり歯根が屈曲していたりすると治療中に破折する場合があります。
破折した器具は取り出してから治療を継続しますが、実際には一部が根管に残った状態のまま根管充填を行い、治療を完了しているケースもあるため注意が必要です。
このようなケースでは、破折した治療器具の一部や残存した組織から感染が広がり、根管治療が失敗する可能性が高いでしょう。
根管治療の失敗で生じる症状

根管治療を終えた歯は被せ物で密閉された状態になるため、もし歯内で感染が再発しても天然歯のむし歯のように表面から見ただけではわかりません。
では、根管治療が失敗した場合には、どのような症状をきっかけに再発に気付く方が多いのでしょうか。
根管治療後に感染・炎症が再発した場合の主な症状は下記のとおりです。
痛み・腫れ
根管治療では神経を含む歯髄を取り除くので、治療後は痛みを感じないと考えている方もいるかもしれません。
しかし、根管で感染が再発した場合の自覚症状として多いのは、歯の痛み・歯茎の腫れです。
この場合、むし歯のように歯の表面への刺激で歯髄に含まれる神経が痛みを感じるのではなく、歯を支えている組織が炎症を起こしたり膿が溜まったりして痛みを感じます。
なお、こうした症状に気付いてから受診するだけでなく、根管治療を受けた後はメンテナンス・クリーニングに通院して定期的に歯科医師による状態確認を受けることも大切です。
根尖性歯周炎

上記のように、根管で炎症が起こると炎症は歯の内部にとどまらず、歯の根元にある根尖孔という小さな穴から顎の骨へ広がります。この状態が根尖性歯周炎です。
根尖性歯周炎は、むし歯を未治療のまま放置することでも起こります。しかし、割合としては根管治療後の再発により起こることが多いとされる病気です。
なお、根尖性歯周炎を起こす前の段階では歯髄が壊死するため、神経の機能も失われて一時的に歯の痛みはなくなります。
しかし、そこで「以前は痛かったけれど、今は痛くないから」と放置すれば、根尖性歯周炎が起こり再び痛みを感じるようになるでしょう。
そのため、気になる症状があった場合には様子をみたり症状が治まるのを待ったりするのではなく、早めの受診をおすすめします。
歯根嚢胞
歯根嚢胞は、歯の根尖周辺にできる嚢胞です。根尖の周囲で起こった炎症が慢性化して発生し、特に上顎の前歯・下顎の奥歯に好発します。
初期のうちには症状がなく、歯科でレントゲンを撮ったときに偶然発見される場合が多いでしょう。
しかし、進行すると歯茎の腫れ・痛み・違和感のほか、嚢胞の内容物を外に排出するために歯槽骨・歯茎内に瘻孔(通り道)ができる場合があります。
瘻孔は嚢胞から歯茎の表面に向かって広がり、最終的には歯茎の表面に嚢胞の内容物が溜まったイボのようなものができるケースもあります。
根管治療が失敗した後の治療法

根管治療が失敗すると、根管から再び感染が広がって歯の付け根・歯槽骨・歯茎にさまざまな症状が現れます。
では、このような症状に気付いて歯科を受診した場合、どのような治療の選択肢があるのでしょうか。
精密根管治療
広く使用されているものよりも機能性が高い器具などを使用して、より精度を高めた根管治療を精密根管治療といいます。
最初の治療から精密根管治療を行う歯科もありますが、一般的な方法で根管治療を行って再発した場合の治療(感染根管治療)として選択されることもある方法です。
精密根管治療で使用される主な器具にはマイクロスコープ・ニッケルチタンファイルなどがあります。
マイクロスコープ(実体顕微鏡)とは、治療する部位を拡大して見るための器具です。口腔内・根管内は暗く、また治療部位が小さいので肉眼での確認には限界があります。
そこで、マイクロスコープを使用することで根管の中が明るく大きく見え、感染組織の除去がより正確に行えるようになるのです。
また、ファイルとは根管内の歯髄を取り除くための器具です。多くの歯科では従来使用されているステンレス製の製品が使用されています。
しかし、ステンレスは硬く、屈曲根(屈曲した歯根)では根管の奥まで届かないことがあります。
そのため、直線的な器具が届きにくい根管の先端まで届くように採用された素材が、ステンレスよりも柔軟性の高いニッケルチタンです。
このように工夫された器具を活用すれば、感染組織の見落としを防ぎ、再発率の低下が期待できます。
歯根端切除術
再発時の状況により、追加で根管治療を行うだけでは症状の改善が期待できない場合があります。
例えば、根尖性歯周炎が重症化したり、歯根嚢胞が大きくなり多くの膿が溜まったりしている場合には、外科的な治療が必要になるでしょう。
根管治療後の再発・歯根嚢胞などに対して行われる主な外科的治療は、歯根端切除術です。
むし歯治療・根管治療は多くが歯の表面から病巣がある範囲を削って治療を行うのに対して、歯根端切除術では歯茎を切開します。
歯根端切除術は歯根の横から歯茎を切開して、根尖の周囲に広がる嚢胞とともに原因となっている根尖部(歯根端)も切除する治療です。
抜歯

上記の精密根管治療・歯根端切除術では症状の改善が見込めない、または治療を行っても歯を残すことが望めないと判断された場合には、抜歯を検討します。
また、歯根端切除術を行っても再発した場合にも、抜歯が必要になる場合があるでしょう。
近年では可能な限り天然歯を残そうとする歯科医院も増えましたが、外科的な治療が必要になった場合には前歯では歯根端切除術、奥歯では抜歯が選択されることが多いようです。
抜歯をした場合には、外見・機能の両面から、抜歯した歯を補綴物で補うことをおすすめします。
根管治療を途中で放棄するとどうなる?
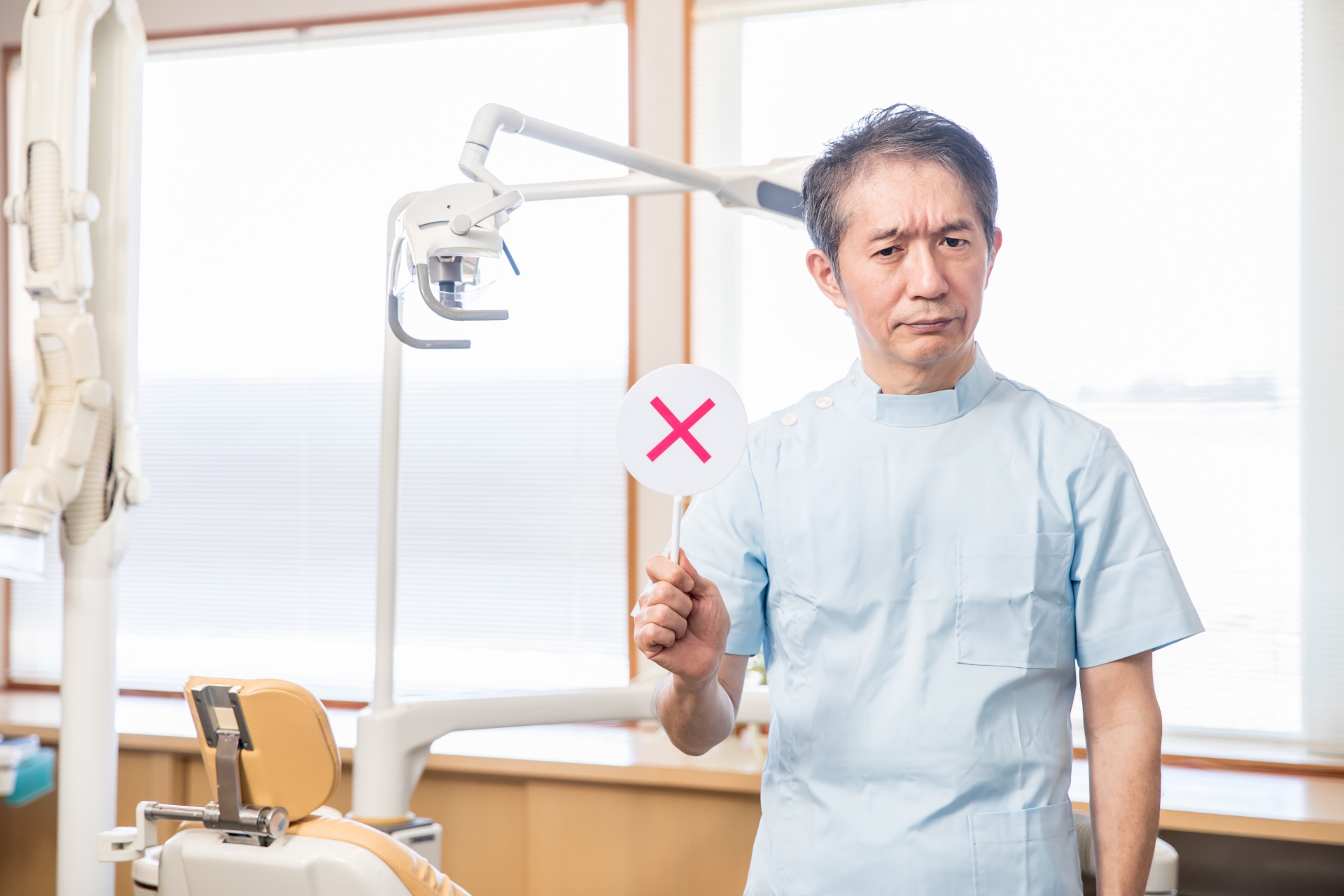
根管治療の治療は、数回に分けて行うケースが多いです。しかし、処置が進むと痛みを感じなくなり、通院のモチベーションが続かない方もいるかもしれません。
では、もし根管治療を途中でやめるとどのようなことが起こるのでしょうか。
むし歯が進行して痛みが悪化する
感染組織を十分に取り除かず、また根管充填など必要な処置をしないまま治療を中断すると、むし歯が進行して痛みが悪化する可能性があります。
抜髄して一度は痛みを感じなくなった場合にも、感染が根尖・歯槽骨まで広がると再び痛みを感じるようになるため注意が必要です。
隣接する歯もむし歯になる
むし歯になると、歯の咬合面から根尖に向かって穴が開いていくイメージがあるかもしれません。
しかし、むし歯はわずかに接している隣の歯にも広がっていくものです。そのため、根管治療を中断すると、最初にむし歯になった歯だけでなく隣接する歯まで失う可能性があります。
抜歯しか選択肢がなくなる
治療を始めた段階では根管治療が適用できる状態だった歯でも、途中で放置して時間が経過すると状態は悪化するでしょう。
その結果、治療の中断後に症状が気になり再診しても、選択肢が狭まり抜歯しか治療法がなくなっている可能性があります。
失敗しないための歯科医院の選び方は?

根管治療後の成功率は、日本国内のデータで約30〜40%といわれています。この数字は、スウェーデンで行われた研究での91%という成功率と比較するとかなり低いものです。
では、どのような歯科を選べば根管治療の失敗を防げるのでしょうか。
根管治療の成功率を上げるためにわかりやすいポイントは、下記の2つが挙げられます。
- ラバーダムを使用している
- 精密根管治療ができる
ラバーダムとはゴムでできたシートで、根管治療の際に治療を行う歯をラバーダムで囲うことで周囲からの唾液・細菌などの侵入を防ぎながら治療を行えます。
また、精密根管治療が行える条件は、前述のとおりマイクロスコープ・ニッケルチタンファイルなどの設備が揃っていることです。
このように治療部位を無菌状態に近づけるための道具を使用すると、新たな感染・感染の広がりを抑え、成功率が高まると期待されます。
特にラバーダムは使用により再発率が下がることがわかっているものの、国内での使用は高いとはいえません。
2019年に行われた調査で、ラバーダムを日常的に使用していると回答した歯科医師の割合は下記のとおりです。
- 日本歯内療法学会(JEA)会員のうち約51%
- JEA指導者のうち約60%
- JEA非会員の約14%
10年程前に行われた調査と比較するとラバーダムの使用率は上がっているものの、経済面からは保険診療のなかでの使用が難しいなどの課題もあり、十分な使用率とはいえません。
このような現状のなかで、精密根管治療の設備だけでなく、根管治療にはラバーダムを使用していると明記した歯科を選ぶことで根管治療の失敗を避けられる可能性は高まるでしょう。
まとめ

歯の中心部にある歯髄が感染・壊死などを起こした場合、従来ならば抜歯が主な治療方法でした。
しかし、近年では根管治療という選択肢が増え、抜髄・根管充填などの処置を行うことで自分の歯を残せるケースもあります。
ただし、根管治療の失敗や治療の中断により、最終的に抜歯が必要になる可能性があるため注意が必要です。
自分の歯を失わないためには、無菌治療の徹底など根管治療に力を入れている歯科医院を選択し、しっかりと必要な治療を続けることをおすすめします。
参考文献