根管治療をした歯の被せ物が取れてしまったら、どのように対処すればよいでしょうか?
根管治療で神経を取った歯はもろくなっており、被せ物が取れたまま放置すると急速に劣化してしまいます。
また取れた被せ物を適切に保管しないと、歯科医師でも付け直すことができず作り直しになってしまうこともあります。
しかし、被せ物が取れても適切に対処すれば治療は短時間で済み、普段から気をつけていれば被せ物が取れるリスクも減らせるでしょう。
この記事では根管治療後に被せ物が取れた場合の対処法・被せ物が取れる原因を解説するので、万が一の際に慌てずに対処する参考になれば幸いです。
根管治療の被せ物が取れた時の対処法

根管治療後に被せ物が取れてしまった場合は驚くでしょうが、冷静に対処すれば多くは心配いりません。
歯科治療では歯の一部を削って詰める材料を詰め物(インレー)と呼び、歯の大部分を削ってすっぽり被せる材料を被せ物(クラウン)と呼びます。
どちらも根管治療で頻繁に使われる材料で、治療後にさまざまな原因で取れてしまうことが少なくありません。
被せ物が取れた時にどうすればよいか、対処法を解説します。
取れた被せ物を容器に入れて保管する
取れた被せ物が手元にある場合、捨てたりせずにできる限り保管して歯科医院に持っていきましょう。
被せ物がきれいに保管されていた場合、そのまま再利用して取り付けることができる可能性があります。
保管の際にほこりが付かないように気を付け、取れた被せ物の変形を防ぐために金属製やプラスチック製の密閉容器に保管するのが適しています。
天然の歯が折れた場合は乾燥しないように水を入れておくなどの対処法がありますが、被せ物の場合は水につける必要はありません。
被せ物が取れた歯で噛まない
被せ物が取れた歯は、大変もろく傷つきやすくなっています。
歯科医院に行くまでの間はなるべく飲食は控え、食べる場合には被せ物が取れている側の歯で噛まないようにしましょう。
被せ物が取れた部分は歯に大きな穴が空いており、根管治療後の場合はその穴は歯の根元にあたる根管まで達しています。
固いもの・粘着質のもの・糖分が多いものなどはなるべく避けて、食後にはうがいと歯みがきをして汚れを落としてください。
歯科医院に行く
被せ物が取れたときには、すぐに歯科医院を受診しましょう。
根管治療を受けた歯科医院に行ければ経過の説明などもスムーズですが、別の歯科医院であっても問題ありません。
歯科医師が歯の状態と取れた被せ物の状態をチェックし、被せ物が再利用できるか・どのような応急処置が必要かなどを診断します。
地面に落ちて汚れてしまった被せ物が再利用できる可能性は高くないため、早く歯科医院に行くことを優先し、落ちた被せ物を無理に探す必要はありません。
根管治療の被せ物が取れたときの注意点
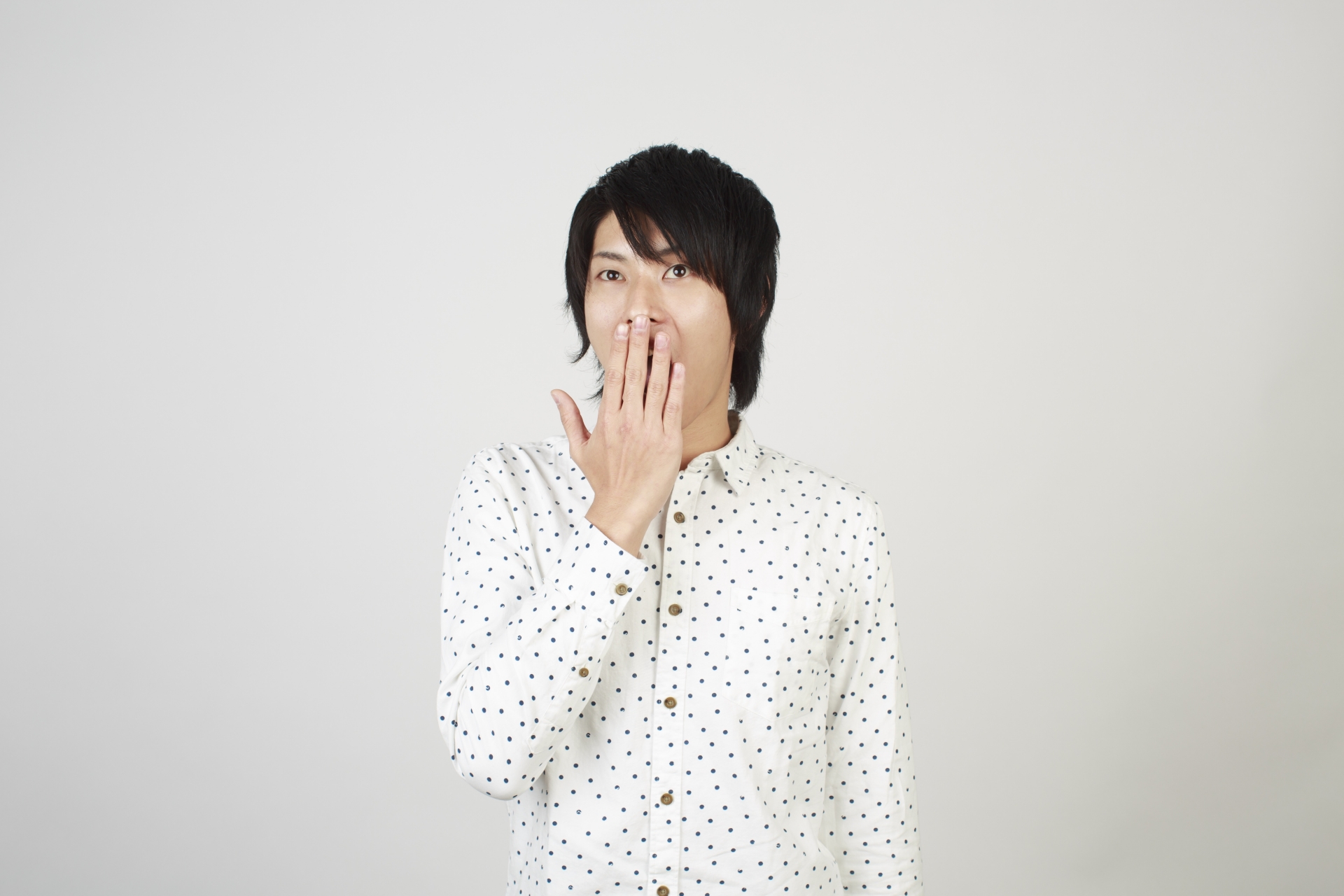
根管治療後に被せ物が取れたときには、なるべく早く歯科医院に行くのが原則です。
患者さんが慌てて対処しようとして、かえって悪い結果になってしまう可能性もあるため、自分で何とかしようとしない方がよいでしょう。
被せ物が取れたときに、やってはいけない注意点を解説します。
被せ物をティッシュで包んで保管しない
取れた被せ物を歯科医院に持っていく際に、ティッシュに包んで保管する方が少なくありません。
しかしティッシュでは被せ物を外力から守ることができず、変形してしまう可能性があります。
歯の被せ物はエナメル質程固くはなく、形状によっては簡単に曲がってしまうのです。
変形した被せ物は再利用できないため、保管する際は丈夫なプラスチック製や金属製の容器が適しています。
被せ物を自分で歯に戻さない
取れた被せ物を、患者さん自身で戻すことは不可能です。
無理やりはめ込もうとして被せ物が変形してしまったり、力を入れすぎて歯が割れてしまったりと悪化する可能性があるので、ご自分で戻そうとはしないでください。
特に根管治療後の歯は神経を取って弱くなっているため、歯の根元が割れてしまう歯根破折のリスクが上がります。
歯根破折になると抜歯せざるを得ないため、せっかく治療した歯を失うことになります。
被せ物を飲み込んでしまった場合は?
取れた被せ物を飲み込んでしまった場合は、歯科医院で歯の処置をした後に内科を受診してください。
ただし呼吸に異常を感じる場合は、気管支に詰まっている可能性があるのですぐに耳鼻咽喉科か呼吸器科を受診しましょう。
歯の被せ物を飲み込んでも、食道に入った場合は数日後に便とともに排出されることがほとんどです。
しかし気管支に入った場合は、気管支内視鏡などで取り出す必要があります。咳によって自然と排出される可能性もありますが、早めに除去した方が無難でしょう。
飲み込んだ被せ物が食道に入るか気管支に入るかは状況によって異なり、レントゲンなどで調べないとわかりません。
飲み込んでから数日経っても出てこない場合は、内科で検査を受けるようにしてください。
根管治療の被せ物が取れる原因

根管治療後に被せ物や詰め物が取れてしまう原因は、治療した歯や被せ物の劣化であることが大半です。
根管治療をした歯は神経がなくもろくなっているので、毎日の入念なケアが欠かせません。
しかしそれでも経年によって被せ物が劣化してしまうのは避けられず、取れる前に再治療する場合もあります。
どのような場合に被せ物が取れてしまうのか、主な原因を解説します。
むし歯になる
被せ物と歯の間の部分には歯垢がたまりやすく歯ブラシも届きにくいため、むし歯になりやすい部位といえます。
歯にセメント質の接着剤を使って被せ物を固定しているので、歯の接着している部分むし歯で溶けることで被せ物も取れやすくなってしまうのです。
大きな被せ物をした歯は特に歯との接着部が見えにくく、歯みがきもおろそかになる傾向がありますので、毎日の歯みがきの際に意識してケアしてください。
また定期的に歯科健診を受けて、むし歯の兆候がある場合には早めの治療も大切です。
歯ぎしり・食いしばりで被せ物が欠損する

睡眠中の歯ぎしり・日中の食いしばり癖がある方は、被せ物が取れるリスクが高くなります。
食いしばりによって歯に強い力がかかり、被せ物が破損して取れてしまうケースが少なくありません。
また被せ物ではなく歯自体が割れてしまい、被せ物が取れる場合もあります。この場合は被せ物の再装着はできず、歯根破折であれば抜歯になる可能性が高いでしょう。
歯ぎしりや食いしばりの原因は明確にはわかっていませんが、精神的なストレスが強く関与しているといわれています。
日々のストレスケアを心がけるとともに、歯を守るためマウスピースの装着などの対処を検討してください。
被せ物・接着剤が劣化している
被せ物にも寿命があり、根管治療から年数が経つごとに劣化していきます。歯の全体を覆う金属製の被せ物の場合、寿命は約10年です。
部分的な詰め物の場合は、約7年で劣化し取れるリスクが高くなるでしょう。
被せ物だけでなく接着剤も劣化していくため、根管治療から数年が経ったら被せ物の交換や再治療が必要になることも少なくありません。
被せ物の寿命を左右する要因は噛む力・酸性度の強い飲食物・日常のデンタルケアなどです。被せ物をした歯で固いものをよく食べていると、劣化が早まってしまいます。
歯みがきだけでなく歯間ブラシやフロスを使用して、被せ物と歯の間もしっかり掃除しておくことを意識しましょう。
固い物・粘着質の物を噛む

被せ物をした歯で固いものや粘着質のものを噛んだときに、被せ物が取れてしまうケースは少なくありません。
根管治療から数年が経って被せ物が劣化していたり、むし歯があって被せ物が外れやすくなったりしているときには、食事によって取れる可能性が高まります。
特に注意したい食べ物はキャラメル・もち・固いパンなどです。食後に歯に詰まったものを取るための爪楊枝でも、被せ物が外れてしまう場合があるので注意しましょう。
また魚の骨など固いものを噛んだときに、歯根破折を起こして被せ物が取れる場合もあります。
根管治療をした歯は割れやすくなっているので、固いものを無理に噛まないように注意してください。
根管治療の被せ物が取れた歯を放置するリスク

被せ物が取れたときには速やかに歯科医院を受診し、応急処置を受けるようにしましょう。
歯科治療の大きな穴が空いたままの歯を放置すると、歯の状態は急速に悪化して歯を失うことになりかねません。
被せ物が取れたままにしておくと、どのようなリスクがあるかを解説します。
むし歯の進行が早い
被せ物が取れたままの歯は、むし歯になりやすい状態です。
歯の表面は通常固いエナメル質で覆われていますが、根管治療ではエナメル質を歯の奥まで削って根元を治療していきます。
エナメル質の下にはやわらかい象牙質があり、象牙質を露出したままにしないように被せ物をしなくてはいけません。
被せ物が取れた歯は象牙質が無防備な状態で、むし歯の原因菌が作り出す酸でどんどん溶かされてしまいます。
また被せ物が取れた歯は形状がいびつで歯垢がたまりやすく、歯ブラシも届きにくくなっているので、むし歯のリスクは高いといえるでしょう。
歯が割れる危険がある

根管治療によって歯の神経である歯髄を除去すると、どうしても歯はもろくなります。
根管には神経と一緒に血管も通っており、血流に乗って栄養が運ばれて歯の土台を強く保っているのです。
その歯髄を除去した後には充填物を詰めて根管を封鎖しますが、血流がなくなるため天然の歯のように自己治癒力がありません。
歯の被せ物は、削った歯の形を整えて外力に耐える役割もあり、被せ物の取れたいびつな歯は容易に割れてしまいます。
割れた歯は初期であれば接着剤などで治療できる可能性もありますが、割れたまま気付かずにいるとむし歯が進行し、抜歯せざるを得なくなります。
噛み合わせが悪化する
被せ物の取れた歯では噛みづらいため、反対側ばかりで噛んでいるうちに噛み合わせが悪化してくる場合があります。
大きな被せ物が取れると、空いた隙間に周りの歯が動いてくるため口腔内全体の歯並びが変わってくるのです。
特に被せ物が取れた歯と噛み合っている歯が伸びてくることを挺出といい、挺出しすぎた歯を戻すことは難しいため、被せ物の治療とともに挺出した歯を抜かなければならないケースもあります。
被せ物を作ったときと比べて周りの歯が動いていた場合、取れた被せ物を再利用できないため作り直しが必要になります。
根管治療の被せ物が取れたときの治療方法

取れた被せ物を持ってすぐに歯科医院を受診した場合、被せ物を再装着するだけで済む場合もあります。
被せ物が取れた原因がむし歯や破損であった場合には、むし歯の治療と被せ物の作り直しが必要です。
取れたまましばらく放置したことでむし歯が進行したり、根管に細菌が侵入したりしていた場合は、根管治療のやり直しとなるでしょう。
被せ物が取れた原因を特定し、その原因を治療してからでないと、再度被せ物をしてもすぐに取れてしまいます。
いずれにしても根管治療後の被せ物の寿命は10年程であるため、こまめに歯科検診を受けながら必要に応じて治療するようにしましょう。
根管治療中の仮蓋が取れた場合はどうすればよい?

根管治療は通常2〜4回の通院が必要となり、治療の途中で仮蓋をします。
歯の表面を削って根管を露出させ、内部に感染した細菌を除去していくのが根管治療の流れです。
治療の途中で根管に細菌が侵入してしまうとやり直しとなるため、仕上げの被せ物をするまでは仮蓋によって根管を封鎖しなければいけません。
根管治療が終わるまでの間は、仮蓋をしたまま飲食をしますが、その際に仮蓋がボロボロと取れてしまい、慌てた経験がある方も少なくないでしょう。
根管治療中の仮蓋は次の治療時まで根管を封鎖する仮のものですので、元々除去しやすいストッピングや水硬性セメントという材料を使っています。
仮蓋の表面がボロボロと取れても、根管を封鎖する部分はしっかり固まっており、問題ないケースがほとんどです。
根管治療中は数週間ごとの通院が前提であるため、次の治療時までに痛みやしびれが出なければ問題ありません。
もし根管治療中の歯に強い痛みが出た場合は、すぐに歯科医院に連絡して受診するようにしてください。
また、仮蓋は数週間しか持たないため、根管治療の途中で通院を辞めてしまうことがないようにしましょう。
まとめ

根管治療後に被せ物が取れた場合の対処法と、取れる原因を解説しました。
根管治療では歯を大きく削って根元を治療するため、治療後には被せ物によって歯を守ることが不可欠です。
その被せ物も10年程で寿命となり、むし歯がある場合にはさらに早いペースで劣化して取れやすくなってしまいます。
被せ物が取れたときも、落ち着いて対処しすぐに歯科医院に行けば問題なく治療できる場合がほとんどですので、慌てる必要はありません。
しかし、被せ物が取れたまま放置してしまうことは歯の劣化を急速に早め、その歯だけでなく歯並び全体に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
根管治療後の歯は弱くなっているため、被せ物が取れないためにも日常のケアを心がけ、むし歯は被せ物が取れる前に治療しておくことが大切です。
参考文献
