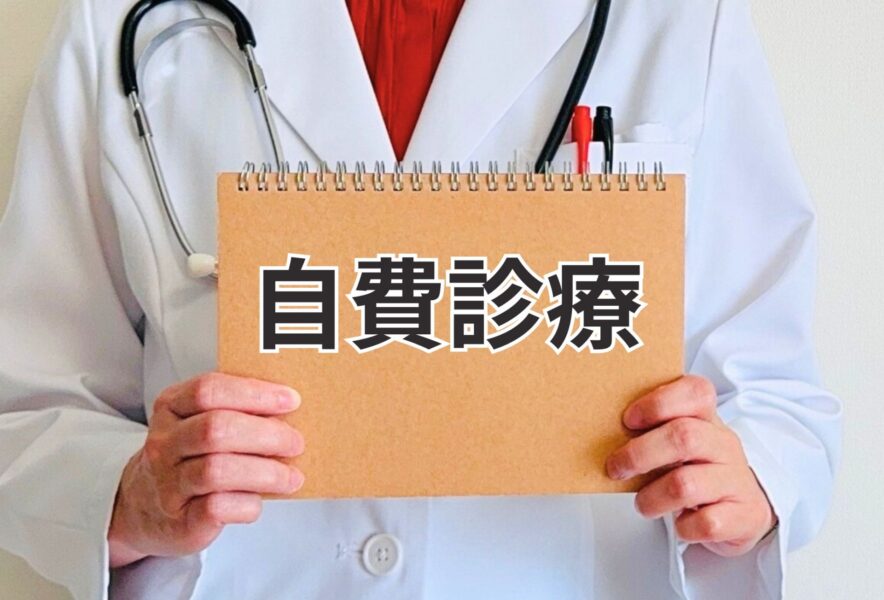根管治療は、重度のむし歯や歯の亀裂、外傷などによって歯髄(歯の神経や血管)が感染したり、死んでしまったりした場合に、歯を抜かずに保存するための重要な歯科治療です。
根管治療には、”保険診療”と“自費診療(自由診療)”の選択肢があります。
本記事では、自費診療による根管治療に焦点を当て、その特徴やメリット・デメリット、費用相場、治療回数、そして保険診療との再発率の違いを詳しく解説します。
自費診療で行われる根管治療の特徴

- 自費による根管治療では、どのような治療を行うのですか?
- 自費診療の根管治療では、成功率を高めるために、先進的な診断機器や精密な治療技術が用いられます。代表的なもののひとつが、歯科用マイクロスコープです。
日本補綴歯科学会の報告でも、マイクロスコープを使えば穴があいた部分の封鎖や、根管内に詰まった器具の除去が可能になり、歯を残せる可能性が高まるとされています。また、“歯科用CT(CBCT)”による三次元の診断も大切です。
CBCTを使えば、従来のレントゲンでは見えなかった根管の形や病変の広がりまで、正確に把握できます。その結果、より正確な治療計画を立てられます。さらに、治療には“ニッケルチタン(Ni-Ti)ファイル”という柔軟性に優れた器具を使い、曲がった根管の奥までしっかりと清掃できます。
- 根管治療の自費診療と保険診療の違いを教えてください
- 保険診療と自費診療の特に大きな違いは、国が定めたルール内で治療を行うか否かです。
保険診療は、使用できる材料や機器、治療時間に制限があり、全国どこでも一定水準の治療を受けられる反面、先進的な治療は行えません。
一方、自費診療にはそれらの制約がなく、成功率を高めるための以下のような適切な治療を選べます。- マイクロスコープによる精密な処置
- CTで三次元的な診断
- ニッケルチタンファイルで清掃
費用は全額自己負担ですが、一回に十分な時間をかけられるため、通院回数が少なく済む傾向にあります。
自費で根管治療を受けるメリット・デメリット

- 根管治療を自費にするとどのようなメリットがありますか?
- わかりやすいメリットは、むし歯や歯周病などの再発リスクを大幅に低減できる点です。
マイクロスコープの使用により、感染源の除去精度が飛躍的に向上し、従来法では見落とされがちだった複雑な根管も徹底的に清掃できます。
実際に、マイクロスコープを用いた外科的歯内療法の成功率は90%を超えるとの報告もあります。
また、歯の寿命が延びる可能性が高まる点もメリットでしょう。
質の高い初回治療は再治療のリスクを減らし、歯へのダメージ蓄積を予防可能です。
将来的な抜歯やインプラントにかかる費用・時間を考慮すれば、初期投資は高くとも長期的には経済的とも考えられます。
さらに、治療後の被せ物に審美性と耐久性に優れたセラミックを使い、見た目の両方を回復できる点もメリットです。
複雑な症例にも対応しやすく、従来なら抜歯と診断された歯も救える可能性が広がります。
- 自費で根管治療を受けるデメリットも教えてください
- 特に大きなデメリットは、保険診療に比べて費用が高額になる点です。治療費は全額自己負担となり、1歯あたり数万円から数十万円かかる場合も珍しくありません。この費用には、最終的な被せ物の料金は含まれていない場合がほとんどです。また、治療を実施している歯科医院が限られる点もデメリットでしょう。
マイクロスコープや歯科用CTなどの高度な設備を導入し、それを使いこなす専門的な技術を持つ歯科医師はまだ多くありません。地域によっては、対応可能な医院を探すのに苦労する可能性があります。
なお、どれほど高度な治療を行っても、成功が100%保証されるわけではない点も理解しておく必要があります。成功率は個人差があり、期待した結果が得られない可能性はゼロではありません。高額な費用を支払うからこそ、成功率に関するリスクはデメリットとして認識しておきましょう。
保険適用外の根管治療を受ける場合の費用相場と治療回数

- 自費で根管治療を受ける場合、費用はいくらくらいかかりますか?
- 自費の根管治療費用は、歯科医院や地域、治療の難易度によって大きく異なります。一般的な相場は1歯あたり6万円〜20万円ほどです。
根管の数が多く複雑な奥歯(大臼歯)は、前歯に比べて高額になる傾向があります。また、初めて神経を取る”抜髄”よりも、過去の治療をやり直す“感染根管治療”の方が、手間がかかるため費用は高くなりやすいため注意が必要です。
自費で根管治療を受ける際は、治療開始前に総額の見積もりをしっかりと確認しましょう。
- 自費の根管治療では何回も通院する必要がありますか?
- 自費診療では1回に60分〜90分以上の時間を確保可能です。多くの時間を確保できるため、自費の根管治療は保険診療よりも少ない通院回数で完了する傾向にあります。
少ない回数で治療が終わるため、診断から根管の清掃や消毒、充填までの一連のプロセスを効率的に進めることが可能です。通院回数が少なく済むのは、忙しい方にとって時間的な負担を軽減する大きなメリットでしょう。
ただし、お口の状況次第では自費診療でも多くの治療回数が必要になる場合もあります。
- 一度の通院で完了する根管治療は、効果が低いですか?
- 一度の通院で根管治療を終える”1回法”の効果が低いわけではありません。むしろ、日本歯内療法学会の歯内療法診療ガイドラインでは、「初回根管治療における1回法は複数回法よりも有効か?」の問いに対し、「弱く1回法を推奨する」と結論付けています。
1回法を推奨する理由は、以下のようなものが挙げられます。- 治療期間中に仮歯の隙間から細菌が再侵入するリスクをなくせる
- 通院回数が減り患者さんの負担を軽減できる
海外では、根の先に病気がある歯でも、1回法と複数回法とで治療成績に有意な差はなかったとの報告が複数あります。
ただし、1回法は適切な診断のもと、徹底した感染対策と精密な処置が行われるのが大前提です。感染が重度で排膿が多い場合など、症例によっては複数回に分けて慎重に消毒を進める方がよいケースもあります。
自費による根管治療後のむし歯の再発率

- 自費による根管治療の再発率を教えてください
- 自費による精密根管治療の再発率は、直接的な統計データは少ないものの、”治療の成功率”から低く抑えられると推定可能です。一般的に、マイクロスコープや歯科用CTなどを用いた自費の根管治療の成功率はとても高いと報告されています。
日本補綴歯科学会が紹介する論文では、マイクロスコープを用いた外科的歯内療法(一度治療した歯の再治療)でも、90%を超える成功率が報告されました。
これらの高い成功率を考慮すると、自費による初回治療の再発率は10%以下に抑えられる可能性が高いでしょう。
- 保険診療での根管治療の再発率はどのくらいですか?
- 保険診療における根管治療の成功率は、自費診療に比べて低い傾向にあると複数の報告が示唆しています。保険診療での再発率が高い理由は、保険制度の制約上、使用できる器具や時間に限りがあり、複雑な根管の見落としや、感染源の完全な除去が困難な場合があるためと考えられます。
日本の根管治療は、低い診療報酬で成り立っている構造的な問題を指摘する声もあります。
もちろん、保険診療でも丁寧に治療を行い、良好な結果を得ているケースも数多く存在します。
- 自費の根管治療のなかでも再発率に差は生じますか?
- 同じ自費診療であっても、再発率に差が生じる可能性はあります。大きな要因は、治療の難易度です。
初めて神経を取る場合に比べ、過去の治療をやり直す”再根管治療”は成功率がやや低くなる傾向があります。また、治療開始時に根の先に大きな病巣がある場合も、治癒が困難になるケースは少なくありません。
もう一つの重要な要因は、術後の修復物の質です。いくら精密な根管治療を行っても、その後の被せ物(クラウン)の適合が悪ければ、隙間から細菌が侵入し再発の原因となります。
根管治療の長期的な成功は、質の高い補綴処置とセットで考えることが、長期的な成功には大切です。
編集部まとめ

自費による根管治療は、マイクロスコープなどの先進技術を駆使して再発リスクを徹底的に抑え、あなたの大切な歯を、一日でも長く守るための積極的な選択肢です。
保険診療が今ある問題を解決する治療であるのに対し、自費診療は歯の未来を守るための投資といえます。
将来の再治療や抜歯のリスク、それに伴う心身の負担や費用を考えれば、決して高くはない選択かもしれません。 もちろん、どのような治療にも100%はありません。
だからこそ、自分が納得して治療に臨むことが大切です。
まずは信頼できる歯科医師に相談し、ご自身の歯の現状と、保険・自費それぞれを選んだ場合の未来について、じっくりと話を聞いてみましょう。
参考文献
- 日本補綴歯科学会.“最先端歯内療法”.日本補綴歯科学会.
- Abudureyimujiang Kuerban, Reziwanguli Yasen.“Research Advances in Microscopic Endodontic Therapy for the Treatment of Dental and Endodontic Diseases”.Francis Academic Press.2025.
- 東北厚生局.“歯科医療の解説”.東北厚生局.
- 日本歯内療法学会.“歯内療法診療ガイドライン”.日本歯内療法学会.2020.
- “わが国における歯内療法の現状と課題”.みずかみ歯科医院.2018-04-07.